
企業は社会や経済の許しがあっての存在
オルタナ20号(2010年8月号)で特集した通り、ピーター・F・ドラッカーも、フィリップ・コトラーも、企業の社会的責任について、本業を通じた遂行を唱えてきた。
「企業は社会や経済の許しがあって存在しているのであり、(中略)社会性に関わる目標は、単なるよき意図の表明ではなく、企業の戦略に組み込まれなければならない」(ピーター・F・ドラッカー『マネジメント-基本と原則』)
「企業の社会的責任(CSR)とは、企業が自主的に、自らの事業活動を通して、または自らの資源を提供することで、地域社会をより良いものにするために深く関与していくことである」(フィリップ・コトラー『社会的責任のマーケティング』)
つまり食品メーカーなら「食育」の地域活動を支援したり、アパレルメーカーであれば、製品のリサイクルや古着を有効利用したりという文脈だ。
自動車メーカーならどうだろう。より環境負荷が低いクルマの開発や、交通事故を未然に防ぐ仕組みづくりなどがそれに当たるだろう。
実際、本田技研工業は、米国1970年大気浄化法改正法(マスキー法)を世界で初めてクリアした自動車メーカーとして知られている。
マスキー法は、排ガスに含まれる一酸化炭素と炭化水素の量をそれまでの10分の1にするという厳しい排ガス規制だった。
厳しい規制を単にクリアするばかりでなく、クリアしたCVCCエンジンをトヨタ、フォード、クライスラー、いすゞなどのメーカーに技術供与までした。
このケースは、マイケル・ポーターの論文『よい環境規制は企業を強くする』(三橋規宏監修・京希伊子訳)の中で、企業が本業を通じてCSRを遂行する好事例の一つとしても紹介されている。
米国で「チャータースクール」を支援
だが、ホンダのCSRはそれにとどまることは無かった。
「私(本田宗一郎)は他人の真似をするのが大嫌いである。(中略)一度、真似をすると、永久に真似をしてゆくのである。これは、企業の体質にとって大変な問題である」(『私の手が語る』講談社刊)
ホンダは、マスキー法クリアによる鮮烈なデビュー以来、世界的には中小メーカーに過ぎなかった同社を温かく迎えてくれた米国社会に対する恩返しを考えていた。
1989年にプロジェクトチームが発足し、そこで整理された2つの方針は「ホンダの現在のビジネスには一切関係ないこと」「資金だけ出すのではなく、自らも汗を流し直接参加できること」をおこなうというものだった。
こうして生まれたのが学費免除の全寮制の教育施設「イーグル・ロック・スクール・アンド・プロフェッショナル・デベロップメント・センター」(イーグル・ロック・スクール、コロラド州)である。
ここで通常の高校教育のシステムにはなじめず困難に直面している生徒たちに対し、個々に適したカリキュラムを用意することで失いかけた未来への希望や夢を取り戻し、かつ、高校の卒業資格を得られるよう支援している。
この学校では、生徒、教師、スタッフがともに学び、責任感を持ち信頼関係を築きながら1つの共同体として生活できる環境をつくっている。ロッキーマウンテン国立公園の大自然に抱かれたこの高校は、まさにアメリカン・ホンダ・モーターの感謝の想いが形になった場所だという。http://www.honda.co.jp/csr/history/eagle_rock/
「ビジネスには全く関係がないCSRとは」
「ビジネスに一切関係がないCSR」。口で言うのとは違って、実際は容易ではない。「本業を通じたCSR」の方が、活動を絞り込みやすいし、何より決定するのに社内を説得しやすい。
「ビジネスに一切関係がないCSR」とは何だろうか。当時のアメリカン・ホンダ・モーターの幹部は、数あるステークホルダーのうち、地域社会に重きを置いたのだろう。それが、前述のようにホンダを温かく迎えてくれた、米国社会やユーザーに対する恩返しだったと推察する。
本田技研工業のCSRサイトを見ると、「喜びの創造」、「喜びの拡大」、「喜びを次世代へ」の実現--に重きが置かれているようだ。http://www.honda.co.jp/csr/
ここで言う「喜び」とは、本田宗一郎が提唱した「三つの喜び」、すなわち創る喜び、売る喜び、買う喜びを指す。
企業がどんなCSR活動を展開していけば良いのか。王道や正解はないと言ってよい。その企業の出自、独自性、地域社会や顧客との関係性によって、何をすれば良いのかが見えてくる。「答えは社内にある」というのが筆者の持論だ。
本田技研工業の場合、その答えの一つは創業者「本田宗一郎」と「米国」の中にあった、ということだろう。(オルタナ編集長 森 摂)




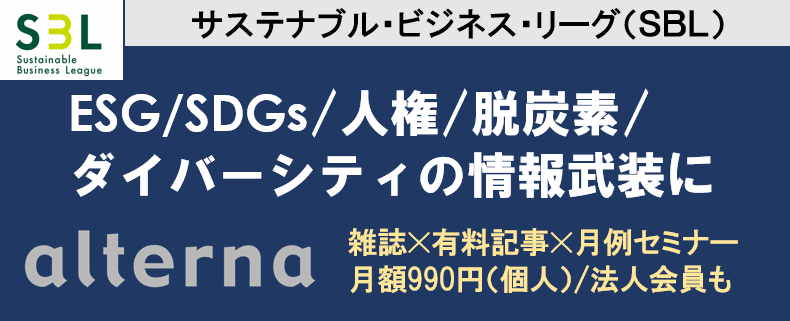

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























