
持続可能な未来をつくるために、環境教育に何が必要なのかを問うシンポジウム「環境教育をラディカルに問い直す」が7日、京都精華大学で行われた。
主催は京都精華大学人文学部・環境教育指導者養成プログラム。4月に出版された『環境教育学』(法律文化社)の著者らがパネリストとして登壇し、社会構造に批判の目を向けることは、持続可能な未来づくりには不可欠だと訴えた。
「環境教育にはもっとできることがある。本来果たすべき役割が果たせていないというのが共通認識」と井上有一氏(京都精華大学教授)が口火を切った。気候変動問題をとりあげ、「日本のC02排出量の半分は、約150の事業所が排出している。節電やレジ袋の削減など、いわゆる家庭の心がけだけで問題が解決する話ではない。社会構造にも目を向けることに環境問題のラディカルさがある」と話し、問題の本質に挑み、責任から逃れない環境教育を訴えた。
これまでの環境教育では、チェルノブイリ原発事故や、水俣病事件の多様な側面が十分に扱われてこなかった、と指摘した細川弘明氏(京都精華大学教授)は、原発問題では、エネルギー供給の側面や、コスト面、技術面だけが取り上げられ、被爆労働者の存在や、原発立地自治体と都市の関係性といった課題が矮小化されてきたと指摘した。
福島で原発事故が起きたことは、さまざまな立場の人に敗北感をあたえたが、環境教育も例外でないと述べ、「敗北感をいだきながら、環境教育を構築していくことが重要」と話した。
林美帆氏(あおぞら財団研究員)からは、小学校に公害教育をよびかけても、反応がいまいちだという報告があった。公害教育は今やることではないと断られるという。その一方で、公害教育の手ごたえも感じている。
あおぞら財団では過去3年間、公害のおこった現地を訪問するスタディツアーを行ってきた。参加者は教員をめざす学生や、現役の教師や社会人。公害の被害者だけでなく、加害企業や行政、支援者らと交流することによって、参加者の社会を見る目は変わる、と公害教育の成果を話した。
コメンテーターの林浩二氏(千葉県立中央博物館学芸員)は、一般的に環境教育の現状を問う批評が少ないなか、『環境教育学』は挑戦的な本だと述べ、「環境教育をめぐる評価はもっと行われるべきだ」と述べた。(オルタナ編集委員=奥田みのり)



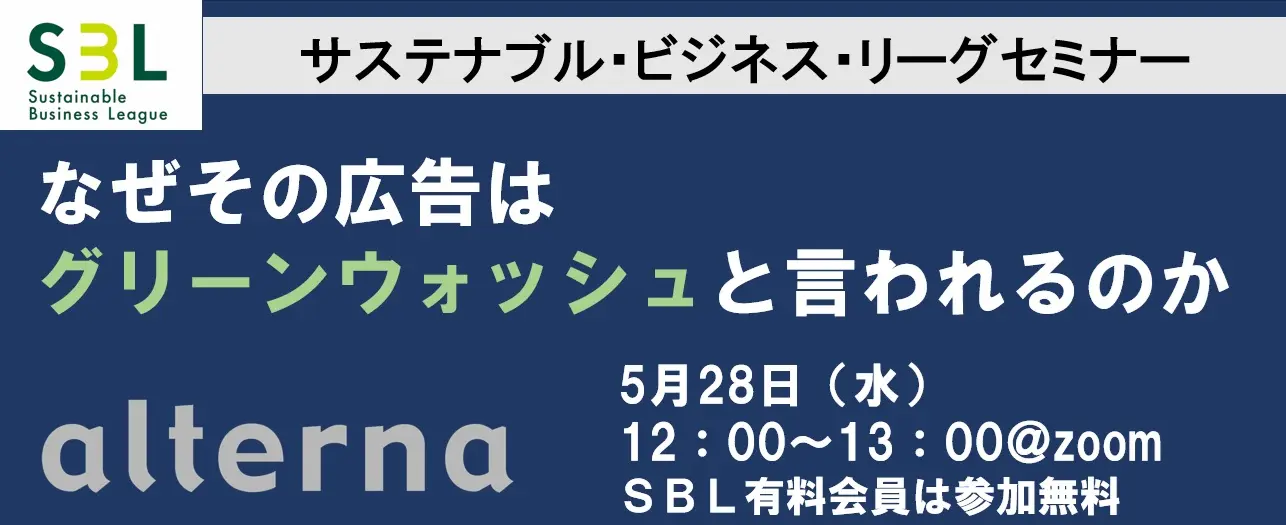


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























