記事のポイント
- エーザイや積水化学工業など「インパクト加重会計」の活用が広がる
- 専門家は恣意的な数字を出すなど「ウォッシュ」のリスクも指摘する
- ウォッシュを防ぐには「計算式を開示すること」が重要となる
エーザイや積水化学工業など「インパクト加重会計」の活用が広がる。環境や従業員、製品についての正負のインパクトを貨幣換算して「見える化」する手法だ。一方で、この手法に詳しい専門家はインパクト加重会計には「恣意的に」数字換算されるというウォッシュのリスクもはらむ。ウォッシュを防ぐには「計算式の開示」が重要であると指摘した。(オルタナ編集部・萩原 哲郎)
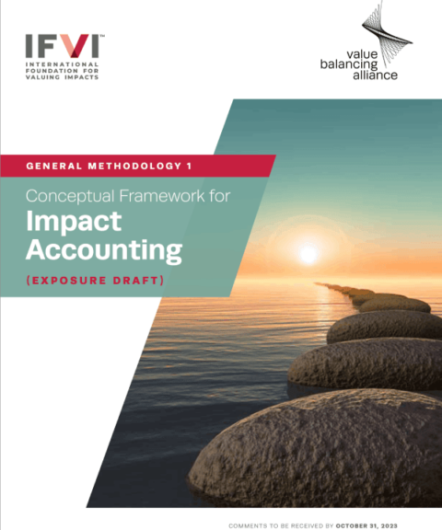
■インパクト加重会計、国際基準の開発が進む
インパクト加重会計は米ハーバード・ビジネス・スクールなどで議論や研究が進められ、現在はインパクト加重会計の国際基準の開発が進む。業種別のガイダンスも作成していて、その第一弾として24年中にヘルスケア向けのガイダンスを作成する予定だ。
インパクト加重会計で測るインパクトは、環境、雇用、製品の3つのカテゴリに分かれる。たとえば環境インパクトではGHG(温室効果ガス)や水、従業員インパクトでは賃金の公平性や職場でのウェルビーイングなど、製品インパクトでは製品の入手しやすさや使用時の環境負荷などをみる。
日本でもインパクト加重会計を導入する企業は増える。エーザイは製品インパクト会計、従業員インパクト会計を公表。ほかにも積水化学工業やSOMPOホールディングス、ヤマハ発動機などがインパクト加重会計を活用して開示を行う。今後、他の企業でも同様の取り組みが広がっていくことが想定される
■企業の導入進む一方で「インパクト・ウォッシュ」のリスクも
インパクト加重会計は企業の環境・社会などへのさまざまな貢献を数値化できることから期待が集まる。一方で、課題もある。そのひとつが、インパクト・ウォッシュだ。
インパクト・ウォッシュとは、インパクト加重会計を用いて環境や従業員、製品についてのインパクトを数値化する際に、恣意的な換算で正のインパクトを大きく見せたり、負のインパクトを小さく見せたりすることだ。企業のPRを目的にして都合の良い数字だけを開示して、負のインパクトは開示しない、といったことも想定される。
現状でウォッシュを指摘されるケースはまれだが、活用が広がればウォッシュの疑いのあるケースが出る可能性もある。
インパクト加重会計に詳しい公認会計士の五十嵐剛志氏は、こういったインパクト・ウォッシュについて「なぜその数字が出てきたのかの計算過程を開示することが重要だ」と指摘する。
計算過程を開示するとともに、なぜその係数を使用したのかなどの説明することで、納得できる数字を示すことができる。外部監査をいれることなどもウォッシュを防ぐ手立てとなる。
■専門人材の不足は導入の足かせに
もうひとつの課題は専門人材の不足だ。すでに導入した日本企業をみると、エーザイは元CFOで「柳モデル」提唱者の柳良平氏がキーマンとなったが、他の企業ではコンサルタントを入れるなどして対応した。
五十嵐氏は現在の国内の人材について「絶対数が不足している」と指摘する。こういった人材の不足は、日本企業がインパクト加重会計を進めていく上でハードルとなりかねない。
大手のコンサル会社では専門の人材をそろえて企業の導入を支援する。五十嵐氏は、日本でのインパクト加重会計の広がりや、ルールメイキングのなかで日本が存在感を発揮していくためにも「インパクト加重会計を専門とする人材の裾野を広げていくことが重要だ」と強調した。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























