記事のポイント
- 186組織がカーボンプライシング(CP)を早期に本格導入するよう訴えた
- この提言には、キリンやリコー、花王など140社が賛同に名を連ねた
- 社名を公開して、CPの具体的なあり方を提言したのは日本で初だ
気候変動対策に野心的に取り組む組織が集まる気候変動イニシアティブ(JCI)は12月5日、政府にカーボンプライシングを早期に本格導入するよう訴えた。JCIは同日に提言を公開した。この提言には、キリンやリコー、花王など140社を含む186組織が賛同に名を連ねた。(オルタナ副編集長=池田 真隆)
日本政府は今年5月に成立したGX推進法に則り、カーボンプライシングを導入する。カーボンプライシングとは、炭素に価格を付け、企業の温室効果ガス排出量を抑える政策だ。企業間で削減した排出量を売買する「排出量取引」と排出量に応じて課金する「炭素税」などがある。
日本では、経産省のGXリーグに参画する企業間での排出量取引を2024年秋から行う。ただし、すでに排出量取引を導入しているEUや韓国などと違い、政府は企業に排出枠を設けない。
企業は、自主的に目標を設定し、排出削減に取り組む。その目標が政府の脱炭素目標である2030年にGHG排出量46%減(2013年比)の削減ペース以上の場合、目標達成した企業は超過削減枠を売ることができる仕組みだ。
ただし、参加も企業の自主性に任せており、目標未達でも罰則はない。未達の企業には、超過削減枠やJクレジットなどの購入、もしくは説明を求める。
政府は2025年に脱炭素目標を更新する予定だ。その更新に合わせて、削減ペースが上がる。こうして2026年から排出量取引の本格化を目指す。
■炭素税を見送り、2028年から炭素の賦課金
2028年には、石油元売りなどを対象に炭素の賦課金を導入する。価格は未定だ。諸外国では、炭素税を導入するが、日本では見送った。税ではなく、賦課金にした理由は、対象企業や価格を柔軟に変えていくためだ。
炭素税として新税をつくると負担率を柔軟に変えることが難しい。租税法律主義があるため、議会の承認を得るプロセスが必要になるからだ。排出量取引は市場価格になるため予測ができない。だから、負担率や対象を柔軟に変えられる賦課金と組み合わせた。
2033年ごろには、発電事業者向けに排出枠の有償オークションを導入する。
カーボンプライシング導入の条件として、岸田文雄首相は、エネルギー関連の公的負担の総額を中長期的に増やさないことを求めた。
エネルギー関連の公的負担とは「石油石炭税」や「再生可能エネルギー賦課金」などだ。石油石炭税は脱炭素化が進めば、再エネ賦課金は環境省の報告書では30年頃にピークアウトを迎える。これらの軽減分に合わせる形で負担率を上げていく。
GX推進法には2年以内に制度や枠組みの見直しを図ると明記した。バックキャスティングでGX化を狙うのではなく、状況を見極めて、都度最適解を探る方針だ。
■リコー役員、「日本の取り組みの遅れは企業の競争力にも悪影響を与える」
JCIは、政府のカーボンプライシングに関する戦略について、「世界で普及が進む炭素税・排出量取引制度と比較すると、同じ水準で排出削減を実現するには依然として不十分な点が多く残る」と指摘した。
提言では、2030年までに日本のGHG排出量の半減と国際競争力を持った経済成長の両立を図るための、カーボンプライシングのあり方についてまとめた。
この提言には、186団体(企業140、自治体9、団体・NGOなど37)が賛同した。そのうち東証プライム企業はキリンやリコー、花王など61社だ。日本のマルチセクターが個別の団体名を明らかにして、カーボンプライシングの具体的なあり方を提言したのは日本で初だ。
リコーの鈴木美佳子・ESG戦略部コーポレート執行役員ESG・リスクマネジメント担当は、「地球沸騰化と言われるほどに気候危機は深刻さを増している。私たち全員が、2030年までの取り組みが地球の将来を大きく左右するとの認識を改めて共有し、スピード感を持って具体的な行動を起こさなければいけない」と強調した。
「ビジネスのあらゆる側面において、1.5℃目標達成に資する取り組みが必要要件となりつつあり、日本の取り組みの遅れは企業の競争力にも悪影響を与える」と話した。
■3つの観点から6原則を提言へ
JCIがまとめたカーボンプライシングに関する提言は下記の通り。
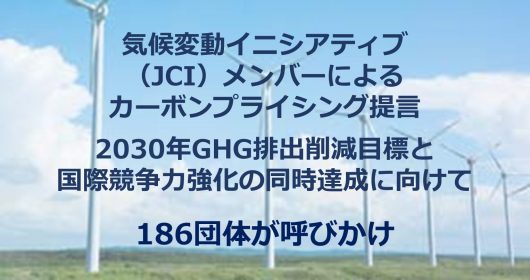
◆
気候変動イニシアティブ(JCI)メンバーによるカーボンプライシング提言
2030年GHG排出削減目標と国際競争力強化の同時達成に向けて政府は、2050 年・2030 年の温室効果ガス排出量削減目標と、安価かつ安定したエネルギー供給、経済成長の同時達成を目指して、グリーン・トランスフォーメーション(GX)の実現を目指している。その一環として、GX 経済移行債による投資支援や化石燃料賦課金、GX-ETSから成る「成長志向型カーボンプライシング構想」が打ち出された。
長年議論されてきたカーボンプライシングの導入に道筋がつけられたことは、大きな前進として歓迎できる。その上で更なる改善を施すことによって、国際的に求められている規模での排出削減に向けて、強力な推進力とすることが期待される。
政府は現在、制度の具体化を進めているが、私たちは、特に以下の 3 つの観点に留意することが必要と考える。
国の温室効果ガス排出量削減目標、とりわけ 2030 年目標の確実な達成:現在示されている自主的な制度では排出削減効果が限定的になり、また導入も遅いため 2030 年削減目標が未達に終わる懸念がある。日本が世界に公約した目標が確実に達成でき、更に野心的な排出削減を求める国際的潮流に合致するような制度が必要である。
排出削減に取り組む企業に不利益のない公平な制度:自主的な制度参加では、コストを負担して排出削減に取り組む企業が、参加しない企業に競争上劣後し、不利益をこうむる可能性がある。一定の要件に合致する全ての企業が必ず参加する公平な制度が求められる。
日本経済の競争力の強化に貢献する制度:不十分な炭素価格では、日本の企業が炭素国境調整措置(CBAM)の対象となることや、国際的なサプライチェーン・投資先から除外されるおそれがある。国際水準での排出削減と再生可能エネルギーの導入が進み、ビジネスの場としての日本の魅力を向上させる制度が必要である。
2030 年までの残り時間は少ない。その中で実効性の高いカーボンプライシングを実現していくためには、既に世界で広く導入されている炭素税と排出量取引制度の経験を十分に活かし、化石燃料賦課金、GX-ETS をより良いものとすべきである。具体的には、今後の制度設計を適切に方向づけるために、私たちは、次の 6 つの原則が満たされることを強く求める。
1)2030 年削減目標達成に向けて 2025 年を目処として実効性の高いカーボンプライシング制度を導入するべき
パリ協定の掲げる 1.5 度目標の達成のため、IPCC は世界全体で 2035 年までの GHG60%削減(2019 年比)が必要であることを示した。こうした知見を踏まえ、日本の 2030 年削減目標を必ず達成するために、現在のスケジュールを前倒しし、2025 年を目処に実効性の高いカーボンプライシング制度を導入するべきである。また、排出削減の実効性を高めるため、世界で先行する排出量取引制度と同様に、GXETS には対象部門からの総排出量の上限(キャップ)を設定し、1.5 度目標の実現にむけたタイムラインに沿って次第に強化されていく制度とすべきである。
2)一定の要件を満たす企業を一律に制度の対象として公平性を担保するべき
排出量取引制度では、公平性を期すために、排出量やエネルギー使用量など、一定の要件を満たす企業全てを一律に制度の対象とするべきである。また、化石燃料賦課金とともに、社名公表をはじめとした履行確保の措置を導入するべきである。両制度の導入にあたっては、二重負担を回避し、事務負担が抑制されるような制度設計が求められる。それぞれのメリット・デメリットが相互に補完され、幅広い企業が削減に取り組む、より公平かつ効果的な制度設計としていく。
3)世界に比肩する水準で将来の炭素価格を明示するべき
企業の投資判断に役立つ形で、IEA が示す 2030 年 130 ドル/t-CO2 など、国際的な水準に比肩する炭素価格を目指すことを導入時に明示するべきである。導入後には、今後の科学的知見の充実や国際議論に沿った適時の見直しが必要となる。また、先進国である日本は、更に野心的な炭素価格を目指すことも望ましい。
他方、GX 推進法では化石燃料賦課金の賦課金単価に上限を設けている。エネルギーに係る負担が過度にならないような配慮は必要であるが、炭素価格を国際的な水準に適合させる上で支障になるのであれば、当該上限は撤廃されるべきである。
4)国際的なルールに適合した制度とするべき
国内外でのルールの違いにより、企業に二重の事務負担や競争上の不利益が生じないよう、化石燃料賦課金と排出量取引制度は、国際的なルールに適合した制度とするべきである。また、EU の炭素国境調整措置(CBAM)の対象にならないためには、他国・地域と同水準かつ同質の炭素価格を目指して、制度対象の一律性と広さ、履行確保措置、炭素価格の引き上げペースなど基本的な制度設計を行う必要がある。制度設計においては、他国・地域で得られた教訓を十分に踏まえるべきである。特にクレジットの使用のあり方は、国際的な動向を受けて慎重に検討するべきである。
(5) 公正な評価のもと排出削減が困難な企業の削減を政府収入により支援するべき
既存技術では排出削減が困難な業種での新技術の開発・普及や、エネルギー転換に伴う中小企業等の負担への対応、再エネ・省エネの導入拡大に向けた取組みの加速を、カーボンプライシング制度の収入で支援するべきである。その際には、1.5 度目標に不整合な技術(石炭火力発電でのアンモニア混焼など)を支援しない等、一定の条件で絞り込む必要がある。また、各支援で見込まれる排出削減の量や時点を明確にした、メリハリの利いた分配が必要である。更に、当該支援は制度設計全体を歪めないようにしなければならず、過渡的なものとすべきである。
(6) カーボンプライシングの立案・評価・更新では透明性を確保するべき
カーボンプライシングに利害関係を有する社会の広範なアクターが、専門的知見や国内外の動向、危機意識、生物多様性や資源循環などの他領域との関係性を共有・議論する場を定期的に設けるべきである。その構成は、特定の業種の企業に偏ることなく、幅広い非国家アクターの参加が求められる。なお、2030 年までの残り時間が少ないことに鑑みて、導入に向けた議論は迅速かつ効率的なものにしなければならない。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























