■被災者の「選択する権利」を阻害
6月24日付朝日新聞は、勧奨地点への帰還を進めるために伊達市が指定の解除を急いだ、と報じた。指定世帯には東電から1人10万円の賠償金が支払われる。同記事は「格差が広がり住民同士の感情の衝突が激しくなれば、復興が難しくなる」との市幹部のコメントを伝えている。
「住民同士の格差が広がると言うのであれば、高線量の地域にとどまり、被ばくを受忍している住民にも賠償金を出すのが筋ではないか」。この問題に取り組む環境NGO「FoE Japan」の満田夏花氏は、23日に同NGOが行った勉強会で、帰還を急ぐ国や伊達市の姿勢に疑問を投げかけた。
住民不在の帰還政策はこれにとどまらない。避難指示解除準備区域に指定された田村市では、除染後の放射線量が目標に届かなかったため、住民は再除染を要望した。これに対して国は住民説明会で「線量計を配布する」と述べ、被ばくを自己管理するよう促したと報じられた(6月29日付朝日新聞)。
住民の意向と無関係に帰還を進める、これらの国の方針について満田氏は「被災者が土地にとどまるか、避難するかを選択する権利を阻害している」と批判。その上で「被ばく基準は科学的な知見も必要だが、住民や市民が参加して決める社会的合意であるべき。低線量被ばくに関する専門家の意見も交え、納得できる被ばくのレベルについて合意を得る必要がある」と訴えている。



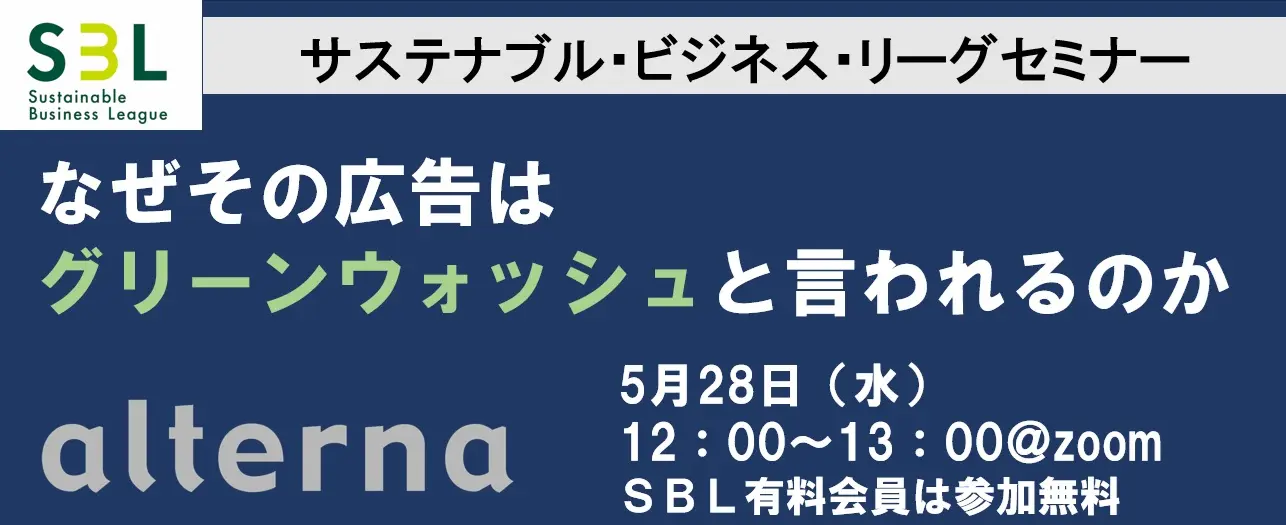


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























