「今日のネット社会は、生産者と消費者が直につながる上では極めて有利。生産者と消費者との交流がネットを介して網の目のように行われる仕組みは、TPP導入にも影響されにくい。生きもの認証システムは生産者と消費者が交流する一つの方法であり、「提携」の現代版として、『あの生産者は安心できる』と評価していくための指標になる」(徳江氏)

9月22、23日に山梨県北杜市で行われた初の同講座は、Bioアナリストの基礎的な知識を学ぶ「ベーシックコース」として開催。生産者、生協や農協の職員、一般企業の社員ら計20人が参加し、環境保全型農業や認証制度などに関する座学や、農場での生き物調査の実習などが行われた。
徳江氏は「Bioアナリストとしての知識を身につけることで、生産者は自らの農業をより深く知り、消費者に自信を持って説明できるしくみを組み立てることも可能となるし、企業であれば環境ビジネスを担う人材を育てる研修の場として講座を活用することもできる」と話す。
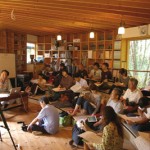
「例えば生物多様性と言われても企業としてどうしたらいいのかが分からない、CSR担当者として何をすべきかが見えない、という場合に、企業が具体的な活動を行う上で講座を学ぶことは効果的ではないだろうか」(徳江氏)
講座は毎月1回行われる予定。年内はベーシックコースを開催し、来年以降はさらに専門性を高めた「アドバンスコース」を実施予定だ。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























