◆国土の約7割が森林におおわれる日本こそ木材の輸出をすべき
―しかし、それでは、また森林破壊につながりませんか。
安藤:熱帯雨林地帯では、6年程度で植林した木が育つので、伐ればすぐに植林をするというサイクルを確立すれば、問題はありません。
日本の場合は伐採まで60年近くかかります。ですから、全体的にバランスよく順番に伐っていかないと、生産量全体では、将来的に厳しくなるので、もっと、計画的に伐採を進める必要があります。
長谷川:海外から輸入する木材は、北米などから入って来ています。しかし、北米など先進国の中には、木材が重要な輸出資源の国もあります。ところが、国土の約7割が森林である日本だけが、なぜか輸出が出来ていません。そのあたりに矛盾があるのではと思っています。
安藤:ただ、今まで高かった国産材も積極的な活用をめざし、一昨年ぐらいから、輸出という出口も見え始めています。
長谷川:日本は、急峻な山が多く、地形条件が厳しいので、そこで搬出の際に価格差が出てきてしまうのは、やむを得ないと思います。例外的に北海道は地形に恵まれているので、コスト的には有利になるのです。
ここ20年間で、国内の木材生産コストは半分ほどに下がっていますし、今後も、まだまだ下がると思います。もちろん、加工コストをもっと下げなければいけないし、規制緩和も必要です。
しかし、技術開発を進めてきた結果、まだ、コスト面での課題は残されていますが、一本の木を余すところなく使い切るという意味では、良い環境になってきています。
◆間伐材利用の「木質バイオマス」は、地域に雇用を生み出す
――間伐材の活用の一つである、「木質バイオマス」についてはいかがでしょうか。

安藤:自然エネルギーの買い取り制度は投資コストに見合う価格に設定されているので、その点では、問題はありません。また、木質バイオマスの場合は、その地域におカネが落ちるという点が重要です。
木を伐り出してチップ化し、発電したものを買い取ってもらえば、現金収入になります。伐採で収入を得る人、その木材を運ぶ人、さらに、木質チップに加工する人、発電する人など、いわゆる山間部で、循環的・完結的に経済が活性化します。
エネルギーの地産地消にもつながります。そういう形ができれば、多少、割高でも地域の中でおカネが回れば、その方がいいという自治体も出てきています。
長谷川:当社の発祥の地・愛媛県新居浜の別子地区では、かなり昔から小規模水力発電(渓流発電)で電力を賄っていました。そういう形で、様々な自然エネルギーを上手に組み合わせれば、地域内で十分に電力を自前で賄えるのではないでしょうか。



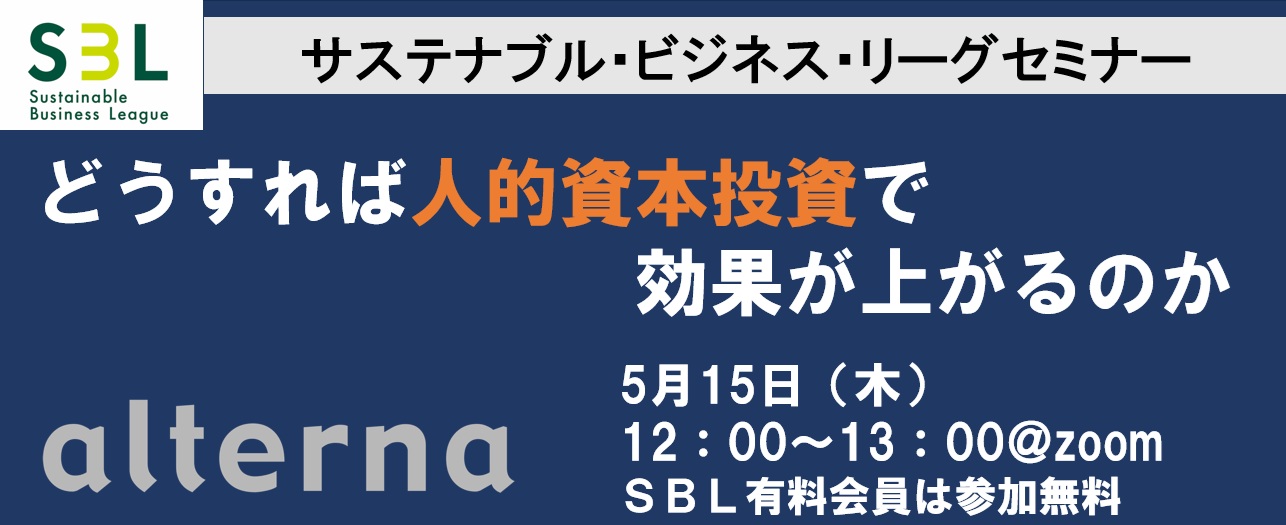


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























