――制作に際して留意した点は
「私の本業は魚類生態学者で、川の中で魚と一緒に泳いで水中撮影したりする。そうしたこともあり、作品を観る人に共感してもらうため、自然の美しさを描くことに力を入れた。また、ダム撤去が実現した背景には、多くの人々の貢献がある。インタビュー取材を通して、一人ひとりが行動を起こすことでダムをも撤去できる、と観る人に伝えたかった。

映画の効用は、観た人が感動して行動を起こしたくなる点にある。私にとって、映画以外に表現方法はあり得なかった。映画を見た人々の中には、実際にそれぞれの地域のダム撤去に向けて動き始めた人もいる」
■ダム依存は非科学的
――(ダム本体に切り取り線をペインティングするような)オシャレな抗議活動は、米国では盛んなのか
「米国でも頻繁ではないが、もっと多くなるといいと思う。日本でも、あのようなデモンストレーションが盛んになるといいね(笑)」
――日本では八ッ場ダムなどの巨大ダム計画が進められている。今なおダムを作ろうとする人々に対して、何が言いたいか
「米国でも新たにダムを造る計画がある。しかし今やダムの建設はムダ。ダムの代替案があるのだから、もっと現代的な方法に注目すべきだ、と言いたい。
実は、ダムから多量の温暖化ガスが排出されている。流域から流れ込む有機物がダムの湖底に堆積し、分解されることでメタンガスが発生する。これは石油を燃やして発生するCO2よりも温室効果が大きい。しかもダム建設で広い森が失われ、光合成でCO2を酸素にする力も弱まる。
ダムが時代遅れなのは、科学的に明らかなこと。今はダム依存から脱ダムへとトランジション(移行)している時期と言える」
――撮影を通じて、自身の中で変化はあったか
「私はカリフォルニアに住んでいるが、これまで地元でネイティブアメリカンの存在を意識することはほとんどなかった。けれども取材を通して、ワシントン州などを流れる河川の流域で暮らす先住民の文化が、ダム建設によって大きく損なわれていることを知った。
しかし同時に、ダム撤去によって自然がよみがえることを通じて、先住民の文化が回復しつつあることも今では知っている」



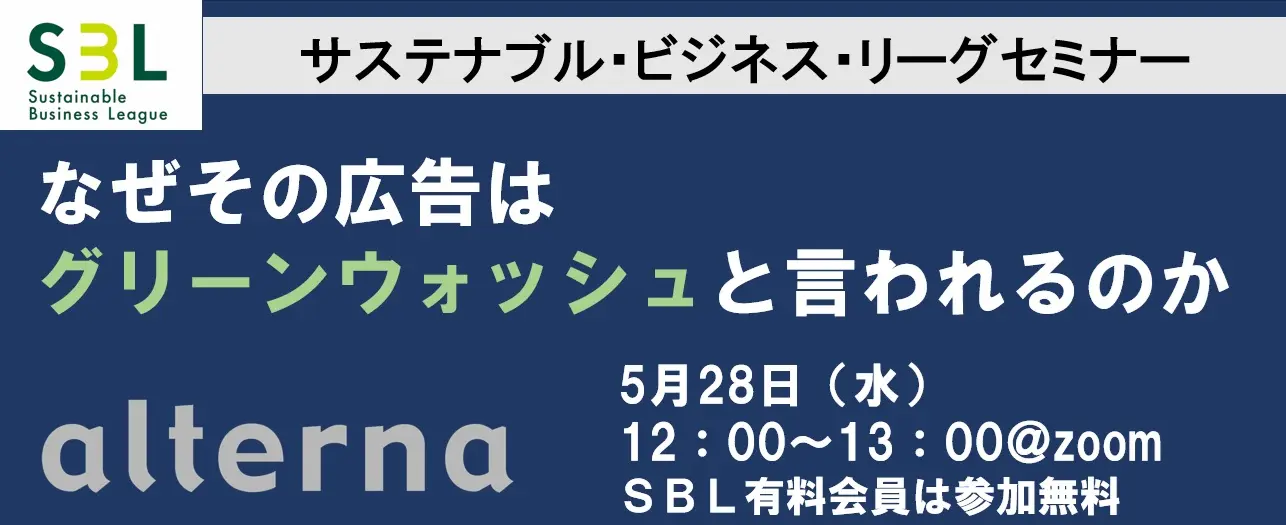


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























