
森のライフスタイル研究所が、長野県伊那市で進めている「アカマツの森 里山再生プロジェクト」は、駒ケ根市の林業会社「アーバンフォレストリー」との協働プロジェクトだ。人の手が入らなくなったことにより、荒廃しているアカマツ林を整備してアカマツの元気を取り戻し、昔のようにマツタケの採れる森づくりに取り組んでいる。(森のライフスタイル研究所=岩崎唱)
森のライフスタイル研究所が実施している森づくりプロジェクトの中で、もっともユニークなのが、長野県の伊那で取り組んでいる「アカマツの森 里山再生プロジェクト」だ。この活動では、普段の森づくり活動でのように植林や下草刈りは行わない。では、何を行うのかというと、熊手を使って林内の落ち葉と腐葉土をひたすらかきだしている。
アカマツに限らずマツ類は、菌根菌と共生することによって荒れ地でも生育できる。むしろ、貧栄養な荒れ地を好む。菌根菌とは、菌根をつくって植物と共生する菌類のことで、菌類とはキノコやカビ、酵母などの仲間のこと。細菌と区別するために真菌とも呼ばれる。
キノコなどの菌類は、植物と違い葉緑体を持たず光合成ができない。したがって栄養分は外部から摂取する。摂取の仕方により共生菌と腐生菌に分けられ、共生菌はさらに菌根菌と寄生菌に分けられる。そして、菌根菌は、外生菌根菌と内生菌根菌に分けられ、さらに外生菌根菌は植物の根と完全共生関係を築くものと、半寄生関係のものがある。
頭が混乱しそうだが、アカマツと共生するのは、菌根菌はマツタケ菌でその子実体がマツタケだ。同じキノコの仲間でもシイタケやナメコ、マイタケなどは腐生菌の仲間で、枯れて朽ちた木を分解して養分として取り入れ生育している。



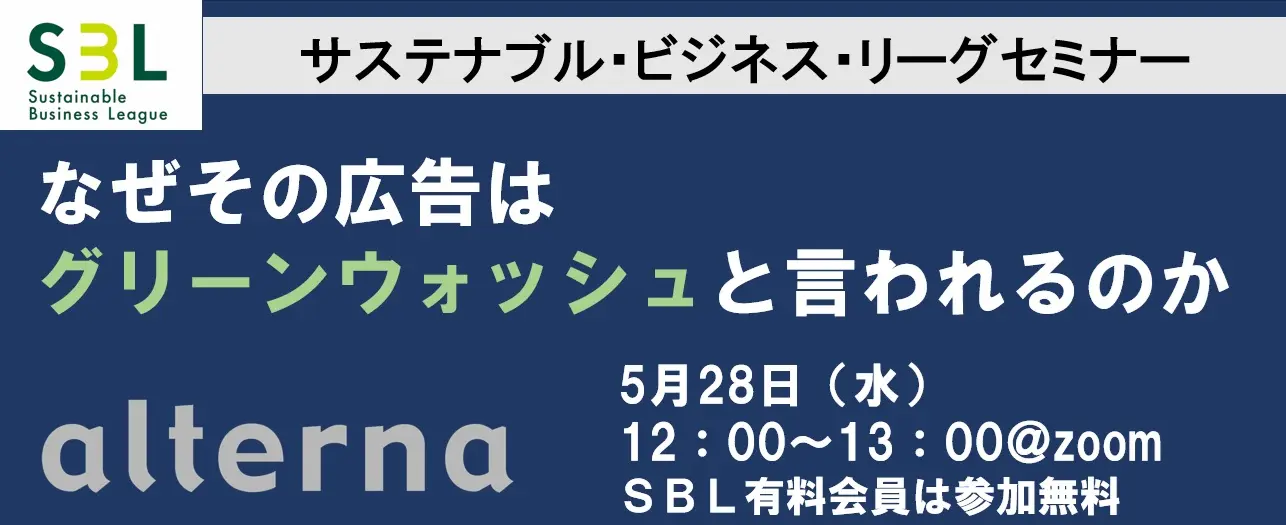


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























