IUCN(国際自然保護連合)が定義する「絶滅のおそれのある野生生物のリスト」には、2014年11月時点で約2万2千種が登録されている。生物多様性の確保は喫緊の事項だ。本コラムでは、味の素バードサンクチュアリ設立にも関わった、現カルピス 人事・総務部の坂本優氏が、身近な動物を切り口に生物多様性、広くは動物と人との関わりについて語る。(カルピス株式会社 人事・総務部=坂本 優)

伊豆諸島の三宅島はかつて、オカダトカゲの楽園だった。1978年夏、私は鳥類学者の樋口広芳先生が東京都から受託した、御蔵島のオオミズナギドリの調査に参加していた。
当時、私は法学部の大学生だったが、学外の動物の研究会で先生の面識を得る機会があり、同じキャンパスにおられたことから、以後、時々研究室にお邪魔してお茶をごちそうになっていた。そんなご縁もあり、荷物運びなどさせていただく口実で、押しかけ「調査隊員」になっていた次第だ。
途中、三宅島で先生旧知の民宿に泊まったおり、今も記憶に深く刻まれている光景を目にした。
それは、翌朝のことだ。初めていただいたアシタバの味噌汁も印象的だったが、はるかに、新鮮な驚きだったのは、庭に幾つかある四角い空き缶(一斗缶)やブロックなどの上で、朝の陽射しを浴びている何匹もの、茶色いトカゲの姿だ。

一斗缶は、食用油や、水煮のタケノコ、コンニャクなどが入っていた、長方形の金属の缶だ。最近は少なくなったが、空になった一斗缶はさまざまなことに活用されていた。鉢植えの鉢代わりにしたり、子どもが魚を飼ったり、あるいは、側面に釘で穴をあけ、蓋をとった上部に網をのせて、かまど代わりにも使ったりと、便利だった。そのため使い終わっても捨てることなく、庭や物置に置かれていた。
民宿の庭にも、空の一斗缶が置かれていて、そのそれぞれに茶色っぽいトカゲがいて、のんびりと昼寝のようにじっとしていた。本土に比べ警戒心の薄い様子に見入っていると、隣で先生が、「三宅島は本当に、トカゲが多い島なのですよ。」とおっしゃっていた。
そのトカゲ――オカダトカゲは現在、三宅島でほとんど見られなくなった。原因は、ネズミ駆除のために移入されたホンドイタチによる捕食だ。



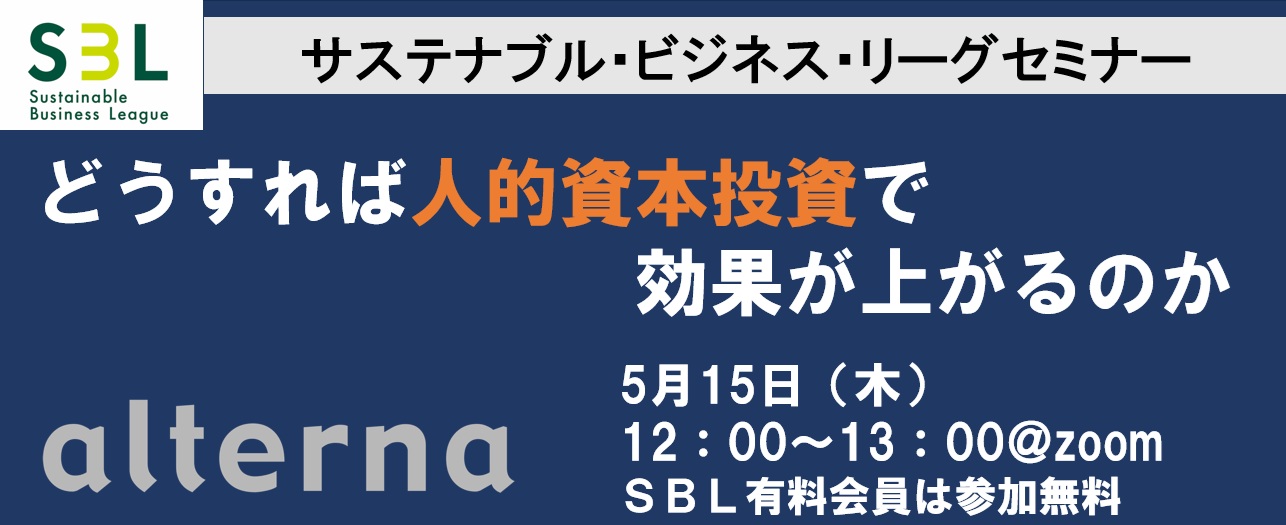


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























