EAAFPは2006年の発足以降、最近では2014年にミャンマー、ベトナムの両国が加わるなど参加国・機関、参加地とも増えており、一見、保護活動が進展しているようにも見える。しかし、大変残念なことに、東アジア・オーストラリア地域フライウェイでは、渡り性水鳥の個体数が年5~9%の割合で減少しており、絶滅危惧種のヘラシギについては年26%もの勢いで減少しているという。
その主たる原因は、黄海沿岸地域の干潟における生息地の急減など、水辺の環境悪化だ。フライウェイ上の生息地が失われるということは、そこを繁殖地や越冬地にする水鳥はもちろん、そこを拠点に移動する渡り鳥にとっても、種の存亡に関わる。
このような状況を踏まえ、昨年1月に釧路で開催されたEAAFP第8回パートナー会議(MOP8)では対策が話し合われた。各国が「参加地」を増やすなど、パートナーが協調してフライウェイ規模の取組みを積極的に進めていくなどの声明が採択されている。東よか干潟の「参加地」登録申請は、これを受けた日本としての取組みの一つでもある。
私たち自身もまた、夏休み(に限らないが)などに個人で、あるいは家族や友人と「参加地」を訪ねることでこの取組みに協力していくことができる。
EAAFPの124か所の「参加地」のうち、33か所は日本にある。この数は、EAAFPの国々の中で最多である。東京都内では、東京港野鳥公園が入っている。

東京港野鳥公園は、2000年にメダイチドリの飛来数が参加基準を超えていたことから、シギ・チドリ類重要生息地ネットワークの参加湿地となった。2006年EAAFPの発足に伴い、シギ・チドリ類の重要生息地として「参加地」となっている。
EAAFPの取組みは、単に渡り鳥の数を増やそうというものではない。自然環境と人々の生活を守り、持続可能な社会を次世代以降に残していこうという地球規模の取組みの一環だ。
もちろん、そのように大上段に構えずとも、「参加地」に飛来する渡り鳥の姿に、季節の変化や自然の豊かさを感じながら、憩いのひと時を過ごすだけでもいい。
そういった何気ない一コマが、大切な日常、貴重な時間として、私たちの生活と記憶の中にさりげなく刻まれ定着していくことも、フライウェイ・パートナーシップが目指す姿に相通じる。



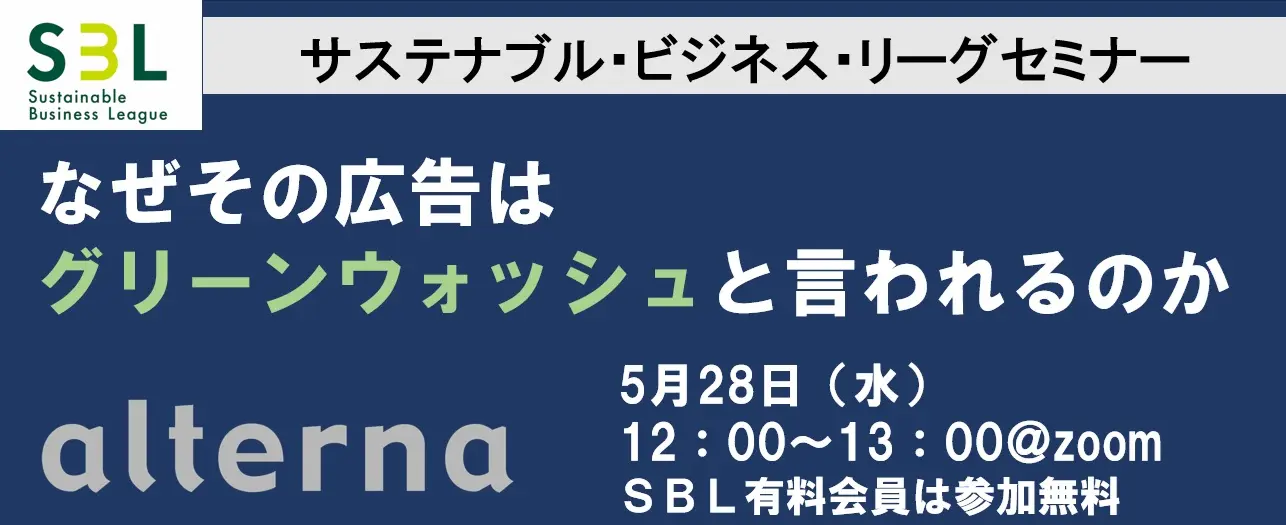


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























