リスの手を借りて森造り?
スタッフの一人が「苗を植えるんじゃなくて、ドングリの種をばらまいた方が楽じゃないか」という。確かにそうだと思う。以前、植樹の代わりにドングリを蒔いたらどうだろうと専門家に相談したことがある。すでに実験をしたことがあるそうで、そこでは山ネズミに食べられてしまって育たなかったとのことだった。しかし、このフィールドは実生(ドングリから発芽して伸びる)の木も目立つのでもしかしたら、と思う。
「リスって冬の間の食料にするためにドングリをあちこちに埋めて、埋めたのを忘れちゃうんで、そこから発芽するっていいますよね」
見たことはないが、よく聞く話だ。
「公園に行けば、ドングリがたくさん落ちているしなあ」
「そのドングリを集めて山に持ってきて山積みにしといて、そこにリスを大量に放せば、リスがいろんなとこに埋めてくれて植林の代わりになるんじゃないか」
「リス造林か、それいいね」
「養蜂業者がハチを連れて日本全国を旅するみたいに、リスを籠に入れて日本の森をめぐってドングリを埋めていくってのはどうだ」
軽トラの荷台に大量のドングリとリスを入れた籠を載せて走る姿を妄想してニヤリとした。ある日の昼休みの与太話だ。

自然をコントロール、するのではなく理解し共存を
さて、先日、樹木図鑑作家の林将之さんの講演会を聴きに行った。その中で森林と動物の関係というテーマの中で、クマは(知ってか知らずか…)森づくりをしている(のではないか)という話題が出た。プロジェクターで、あちこちに枯れ木がある人工林の写真が映し出された。ツキノワグマが樹皮を剥いてしまい枯れたものだという。遠目に見るといい塩梅?に間伐しているように見えなくもない。
また、クマは木の実を食べるために樹木の上に棚をつくる。これによって林冠にギャップができ、そこから日光が入り下層の植物が育つという研究報告※もある。生態系の中では様々な生き物がうまくバランスをとり、自然を持続させている。逆を言えば様々な生き物がいるから自然は持続することができるともいえる。林さんの講演でも「自然をコントロール」するのではなく「自然を理解し共存」していくべきだという話で締めくくられ、大いに得心した。
※ 林冠ギャップ創出者としてのツキノワグマをめぐる生物間相互作用ネットワークの解明
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-26450203/



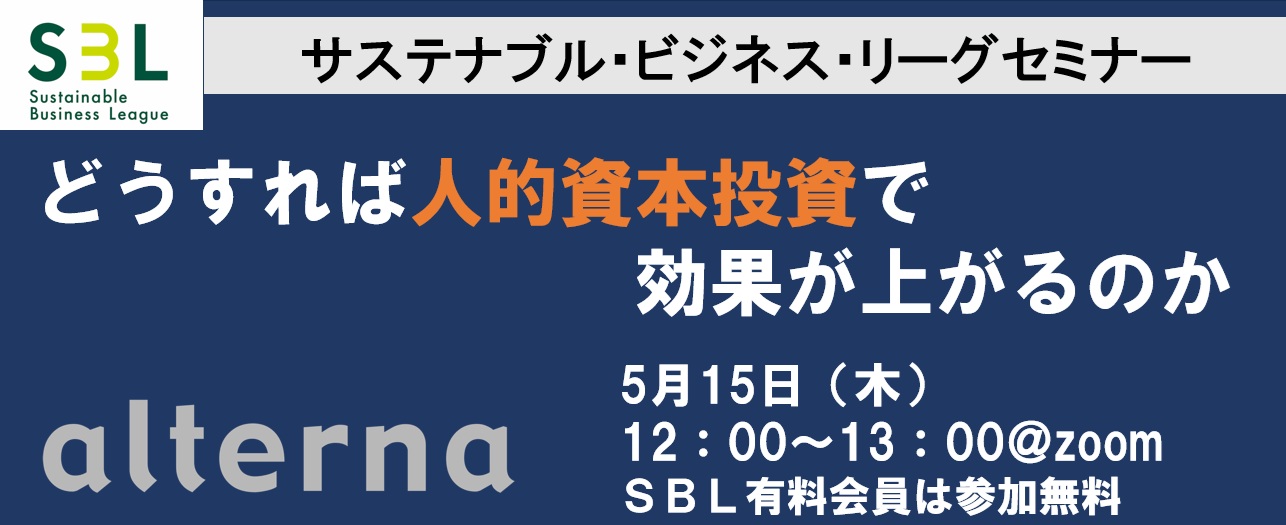


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























