山仕事でいちばん楽しみなのは昼飯だ。肉体を酷使するので昼はしっかり1時間休む。仲間と景色を眺めながら食べる昼飯の美味しさといったら、それがコンビニで買い求めたお握りであろうと、カップラーメンであろうと格別だ。また食後に仲間と交わす他愛もない話が楽しい。先輩の体験談に耳を傾けることもあるし、地域の噂話に花を咲かせることもある。この山をどんな山にしていこうかなど真面目な話もするし、しょうもない与太話もする。まあ、与太話の方が多い。その日の話題は「リスに森を造らせる」だった。

地拵え時に感じる罪悪感
長野県佐久市大沢財産区の、とある森では、ヒノキやカラマツを伐採した跡地に企業の力を借りてコナラを植樹している。木材を産出させる森ではなく、地域の人たちが近い将来、薪ストーブ用の燃料(薪)を調達できる「薪(たきぎ)の森」にしようという計画だ。
その日は私と地元の協力スタッフで、企業ボランティアの方たちが秋植えをするための準備作業をしていた。木を植える前には、森の中に残されている枝や幹を片付け、伐採後に自然に生えてきた木もきれいに刈り取って、一旦更地にする「地拵え(じごしらえ)」という作業を行う。更地にした方が木を植えるのが楽だし、下草刈りなど後の作業もしやすい。しかし、伐採跡地にある広葉樹の切り株からは“ひこばえ”がたくさん出てきているし、昔落ちたドングリから発芽して伸びてきた木もある。日本の気候風土だと、放置してままでもけっこう木は生えてくるのだ。こうした幼木を、植林の邪魔になるからといって伐ってしまうのは、いつも少々心が痛む。
放っておいても森になるのか?
また、この森の植栽地の一角で3年前の植樹活動のときにオオスズメバチが地中に巣をつくっているのを見つけ、危険なのでその10m四方をテープで囲って立入禁止にした。その場所は、植樹はもちろん夏の下草刈りもしていないので、切り株から萌芽更新して育ったコナラや日当たりのいい場所に生えてくるタラノキや種が飛んできて生えたカラマツなど様々な木が無計画にススキやタケニグサなどの雑草に混じって生えている。これを見ていると、今やっている作業に少し疑問がわく。
わざわざコナラの苗を購入して、地拵えをして植えなくても、放っておけば萌芽更新や実生でコナラやクヌギが生えてきて雑木林になるのでは、と思う。「植えない森づくり」(大内正伸著 農文協刊)という日本の気候風土と現代事情に見合ったエコロジカルな林業を提案する書籍もでている。木材を生産するスギやヒノキは、ほったらかしでは生えてこないので人が植える必要があるが、広葉樹の森をつくるのなら、場所と場合によっては放置という手もあるのかもしれない。もちろんコナラの純林にはならないが、適切な選別や下刈りをしてやれば案外いい森になるかもしれない。

リスの手を借りて森造り?



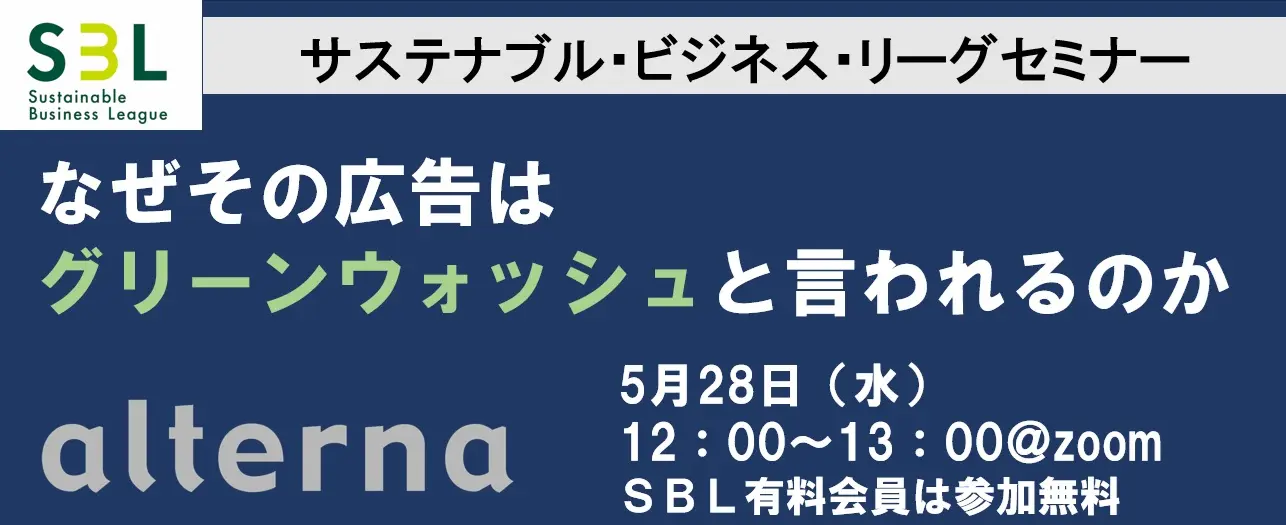


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























