■猫が地域コミュニティづくりの後押しをする

なぜ、排他的?ともとれる条件を付けたのか。オーナー兼プロデューサーの東大史氏は「猫の存在を通じて人と地域を結び、それぞれの幸せを実現し、場所としての価値を高めていく居職住複合型賃貸住宅というのがSanchacoのコンセプト。“猫の幸せ”のために居住者が保護猫を家族として迎え入れる。“人の幸せ”のために耐火・防災に対応した環境適応型住宅として長く安心して住むことができるようにした。
また“地域の幸せ”のために1階にカフェやスナックを営業できるレンタルスペース“猫の額”やDIYワークショップ、多世代交流イベントを開催できる共用スペース“にくきゅう”を用意している。
さらにクリエイティブワーキングスペースもあり、ここでも譲渡目的の保護猫が飼われる。外を歩く人から中にいる猫が見えるように設計されていて、猫を媒介として地域住人とSanchaco居住者の交流が可能となり、ただの塒(ねぐら)ではなく地域の中で暮らしていく居住空間として設計した。居住者が出張や旅行などで長期間留守にする場合を想定して、猫を預かり世話をする相互扶助型近隣コミュニティの形成もめざす」と話す。
東氏は、10年以上日本各地で地域活性化の専門家として様々な課題に取り組んでこられた。その中で感じたのが、一緒になって育んだり、助けたりする対象があると、利害を超越できるということ。猫という存在がともすると対立構造に陥りがちな既存住民と新規住民の仲を取り持つというわけだ。
■猫だけがSanchacoの魅力ではない
猫好きにとっては、どうしても猫に注目してしまうが、Sanchacoの魅力は猫だけではない。JAS構造材を用いた木造建築で、燃え代設計による準耐火構造となっている。木造だが耐火素材をふんだんに使用し、住む人のプライバシーに配慮した防音性、温熱環境に配慮した通風計画など猫にとってもヒトにとっても快適な居住空間となっている。
東大史氏が目論んでいるのは、不動産を賃貸するだけではなく、猫が象徴する快適な暮らしを提供することなのだろう。1階部分のレンタルスペース、共用スペースでも、地域住民も巻き込んだ様々な“仕掛け”を考えているようだ。そうしたコミュニティから新しい働き方、暮らし方が提案され、ポストコロナ禍時代の都市生活のデフォルトとなっていくかもしれない。
◆これからのQuality of Lifeを考えたい



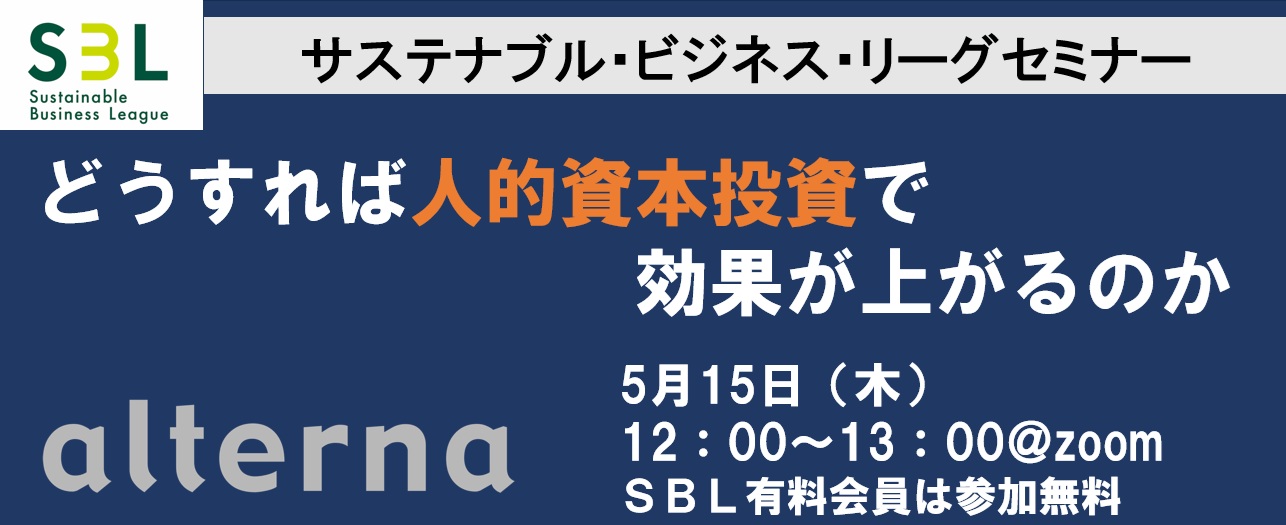


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























