■ソムリエ協会は一転、慎重姿勢に
田崎真也会長が語る。
「教本は呼称資格認定試験のためのものである。ソムリエ協会は学説の真偽を認定したり、それについて公式にコメントしたりする立場にはない。福岡説については、そのような論文が発表されたと紹介しただけ」という慎重な姿勢を崩さない。協会内で議論でもあったのか、「福岡説は事例としてはおもしろいが、同じような話が各地にあり、福岡だけを特別に取り上げるのは中途半端だし不公平。来年の教本では、この部分は削除するよう既に指示した」

注意深いというより後ろ向きに近い。この反応を知ったら、全国のワインファンはがっかりだろう。
ワインについては博学で知られる田崎氏とあって、日本のワインの歴史には通じている。「水戸黄門が飲んだ葡萄酒もワインではなく梅酒のようなリキュールだった。新たに発酵道具や種、醸造プロセスを記した文書などが発見されない限り、福岡の葡萄酒をワインと確認することはできない」と話す。どうやら、個人的には、福岡の葡萄酒も同じように混成酒と考えているように見受けられる。
それも当然かもかもしれない。日本人とワインの最初の出合いは室町時代後期の「珍蛇(チンタ)酒」や「南蛮酒」、つまり、スペインやポルトガルから伝わった赤ワインに遡る。1549年に鹿児島に到着したフランシスコ・ザビエルが薩摩の守護大名・島津貴久にワインを献上した記録も残っている。また、宣教師によってもたらされたワインが織田信長や豊臣秀吉、徳川家康らに嗜好品として飲まれていたことも知られている。
これらはすべて海外物である。江戸時代に飲まれた国産の葡萄酒は、前述の水戸黄門の例をはじめ、ほとんどがワインもどきなのである。
日本ワインに詳しい仲田道弘氏は、その著「日本ワイン誕生考」(山梨日日新聞社)で、中国の「清代食譜大観」や1697年出版の日本版食物本草の大辞典「本朝食鑑」などを参考に、「江戸時代、葡萄酒と言われたほとんどの酒は、ブドウを発酵させておらず、焼酎や日本酒に葡萄果汁を混ぜたものだった」としている。いわば、ワインのプロの間では、江戸時代の葡萄酒はワイン、つまり醸造酒ではなく、混成酒というのが常識になっているのだ。
この本でも、小倉藩細川家の葡萄酒について言及、「野ブドウの2ヵ月程度かかっている。(略)ワインではなく、果汁と焼酎などを混ぜ合わせた混成酒の可能性が高い」と主張している。自家用の薬用酒なら2週間の発酵で十分だし、醸造酒の根拠のひとつとなっている黒大豆に触れていないのも難点である。新しい史料の発見に対し、もう少し正対してもよさそうな気がする。
■日本ワイン史の専門家「判断難しい」
それではと、日本ワインを愛する会会長、日本輸入ワイン山本博氏協会会長にして、「新・日本のワイン」(早川書房)、「ワインの世界史」(日経ビジネス文庫)などの著作があり、日本のワインの歴史に詳しいに判断を仰いだ。
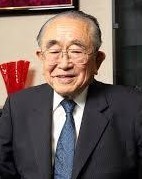
「福岡の小倉藩細川家が江戸初期に製造した葡萄酒が日本初のワインかどうかは情報不足で現時点で判断するのは難しい」と前置きして、① 江戸初期にワインの複雑な発酵のメカニズムを理解していたかどうか ② 出来上がったものが本物のワインと同じものか ③ なぜ一般に普及しなかったのか――などの疑問点を指摘した。
特に発酵プロセスに関して、山ブドウは糖分不足で発酵がうまくいかず砂糖を加える場合もある。また、小粒で果皮が厚く水分が少ないため圧搾作業が困難、これをどうしたのか。また、酵母菌がうまく働かないと雑菌が繁殖して腐敗してしまうが、これを防止する環境を確保でたのかどうか、さらに1次発酵の後、酸を和らげるマロラクティック発酵を行うのが普通だが、そういう知識があったのかどうか、といった問題があったはずと述べる中で「明治政府の殖産興業政策の一環でワイン生産が推奨されたが、製造は困難を極め、大半は挫折してしまった。それほどワイン造りは難しい」と強調した。
こう見てくると日本ワインの歴史に詳しい人たちは、江戸時代にワインが存在したことに懐疑的な傾向があるようだ。
■醸造専門家は前向き評価






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























