◆論説コラム
■「日本初のワインは福岡」説を教本に加筆
日本最古のワイン史料は江戸初期の福岡である、という後藤典子氏の衝撃的な内容の論文「小倉藩細川家の葡萄酒造りとその背景」はメディアでも取り上げられ話題を呼んだ。日本ワインの発祥の地は山梨県で、1874年、山田宥教と詫間憲久のふたりが本格的なワイン造りを始めたというのが定説だったから、大変なニュースである。
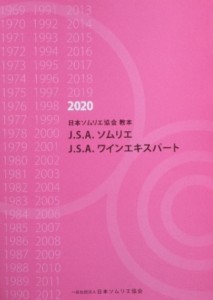
日本ソムリエ協会としても当然取り上げないわけにはいかない。2020年版教本の日本ワインの歴史の項に、後藤論文に触れ「これが事実だとすると、初の本格的なワインは1627年には、福岡県において造られていたことになる」と書き加えられた。
執筆者は遠藤利三郎氏である。「すぐに論文を取り寄せて読み、醸造酒に間違いないと確信した。歴史が250年もさかのぼる大事件だと思った」と、興奮気味に語る。事実なら、という但し書きを入れたのは、江戸時代の葡萄酒はワインではなく焼酎にブドウ果汁を漬け込んだ合成酒だと主張する専門家も多く、断定するのは時期尚早との判断が働いたからである。
「もちろん、ワインに間違いないと思う。論文は黒大豆=写真=の酵母を使い、発酵を促進させたなど詳細だ。また、ガラシャ夫人がクリスチャンで宗教が関係しているだけに、ワインの醸造に詳しい宣教師も存在しただろうし、焼酎など混ぜずに本格的な造り方をしたはずだ」

この内容を教本の編集委員長の森覚氏がフォローアップ・セミナーで解説したというのが経緯である。因みに、教本は、ソムリエ協会が毎年実施しているソムリエやワインエキスパートの資格試験の教科書で、750ページの分厚な本である。年ごとに内容が更新されることから、既にソムリエ資格等を持っている人もフォローアップ・セミナーで最新情報を入手する仕組みになっている。関係者の間で大きな話題になったのも頷ける。
2000年以降、大変な日本ワインブームで、長野や北海道で若者によるワイナリーの新設が相次いでいる。海外でもコンクールで入賞する日本ワインが相次いでいる。食文化やワインの知識の普及などに取り組んでいるソムリエ協会にとっても、日本ワインの歴史に関心が集まるのは歓迎すべきことだろう。福岡説の掲載にかけた熱い思いを探るべく取材すると、思いがけない反応が返ってきた。
■ソムリエ協会は一転、慎重姿勢に






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























