
――これまでは消費者を騙す悪質な事業者を規制する印象が強かったのですが、どのような働きかけで事業者の自主性を伸ばしますか。
悪質な事業者への対策は継続するのですが、健全な事業者に対しては、向き合い方を変えていった方がいいのではないかと考えました。企業が生き残るためには、消費者の声をくみ取ることが必須です。そこで、従来から、消費者庁として、法令を遵守して、消費者目線で現場の声を集めることを消費者志向経営として提唱してきました。
このたび、一橋大学大学院の名和高司客員教授から助言を受けながら、その考え方にSDGsの指標も加えて、将来世代のことも踏まえた経営を新たな消費者志向経営としました。これは消費者と共創・協働して社会価値を高める経営です。
このフレームワークをもとに経営者がガバナンスとサステナビリティを意識することで、達成年まで残り10年になったSDGsへの貢献やエシカル消費の促進につながります。現在、消費者志向経営を宣言している事業者は158社(2020年7月末)です。
ESGのうち、日本企業はEとGは力を入れやすいのですが、Sに関する取り組みは何をしたらいいのか考えあぐねているという話を経営者から聞きます。そこで、消費者志向経営を宣言した事業者の表彰制度を2018年から始めています。
初年度の優良事例として、内閣府特命担当大臣賞に輝いたのは花王です。お客様相談窓口に寄せられた声をデータベース化して商品開発に生かした仕組みや環境負荷やユニバーサルデザインの取組みが高く評価されました。
2019年度は徳島市にある広沢自動車学校が大臣賞を受賞しました。この学校では、指導員にスマートフォンを支給して、顧客とはLINEでコミュニケーションを取ることを推奨しています。指導員は卒業後も定期的に交通安全の呼び掛けを送っており、その結果、卒業生の事故率は徳島県内の平均事故率よりも0.3ポイントほど低いことが分かりました。
若い人はメールよりもLINEに慣れているので、消費者側に寄り添ったコミュニケーションのあり方が評価されました。
これらの事業者の取組みは社会性が高いとも言えるのですが、事業活動としては極めて合理的な取組みとも言えると思います。



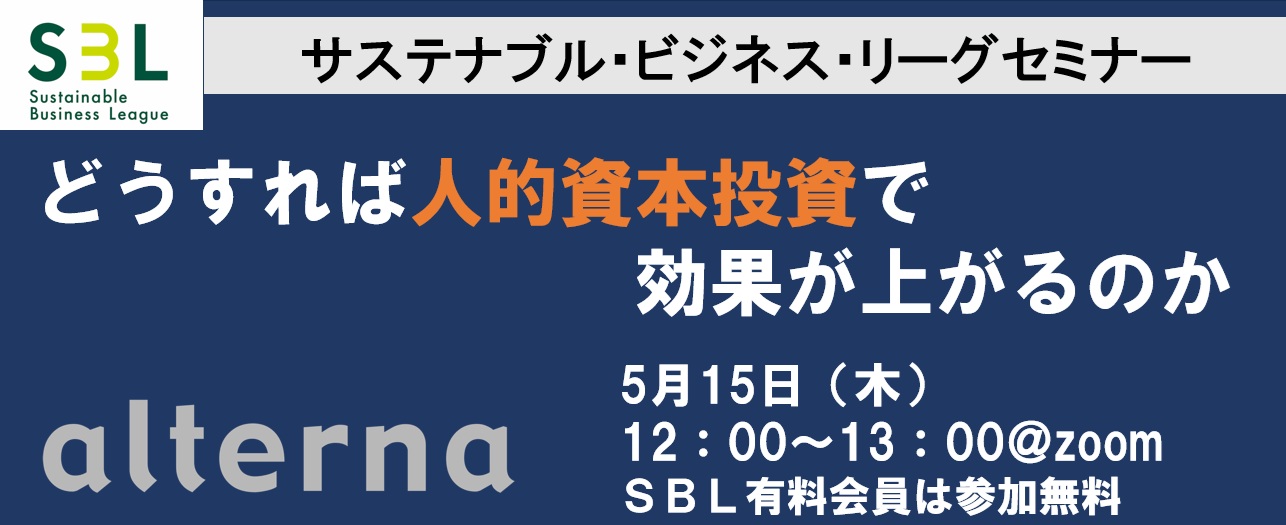


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























