菅首相の脱炭素宣言以降、日本でも「2050年に脱炭素を目指す」ことが上場企業のデファクト・スタンダードになりました。今まで日本企業は、自然エネルギーへの切り替えをコスト増と捉える向きもありましたが、フィンクCEOの文章を読むと、それは未来に対する投資であることが分かります。

©2020 Bloomberg Finance LP
そして、この文章はCSRとESG、そしてSDGsというこの10年のサステナビリティ用語を、見事に説明しています。
「社会に損害を与える企業はいずれ自らの行為に対するしっぺ返しを受け、株主価値を棄損することになる」の部分は、CSR(企業の社会的責任)と「広義のコンプライアンス」を示しています。
広義のコンプライアンスとは、狭義の「法令順守」「社内規則」に加えて、社会からの要請や社会のニーズに応えることを指します。たとえ法的に処罰されることはなくても、守らなければならない規範を指します。
SDGs(持続可能な開発目標)も、一種の社会からの要請であり、グローバルな社会的課題に関する世界の共通言語と捉えれば良いでしょう。
「ステークホルダーに真摯に向き合う企業」は、ステークホルダー・エンゲージメントです。たとえNGO/NPOやメディアから批判を受けても、逃げることなく、対話を重ね、前向きに取り組む企業が評価を受けるのです。
「顧客とより深くつながり、」の部分はCS(顧客満足度)を指します。オルタナでは、CSの延長線上として、SS(社会満足度)があると考えています。社会から存在を期待される企業は容易に無くなりません。その逆も然り、です。
パーパス(存在意義)の浸透がESG経営の根幹
「究極的には、企業理念が長期的な収益性の源泉となる」の部分は、パーパス(存在意義)を従業員に浸透させることがESG経営の根幹であることを表しています。IIRC(国際統合報告委員会)も同様の主張をしています。
このラリー・フィンクCEOの文章は、2020年12月に発行した「CSR検定2級テキスト」(1章の1)の拙文にも引用させて頂きました。同時に、オルタナ63号第一特集にも掲載しました。オルタナ63号第一特集では、同じ文章から次のフレーズも引用しました。
「サステナビリティに関連する投資リスクが増大する中、投資先がサステナビリティに関連した情報開示や事業活動で十分な進展を示せない場合には、経営者と取締役に対して、反対票を投じることについて、より積極的に検討する」
弊誌63号の第一特集は、この声明を受けて世界がどう変わったか、「SX(サステナブル・トランスフォーメーション)」という言葉を使って説明しました。日本政府もSXに向けて動き出しています。



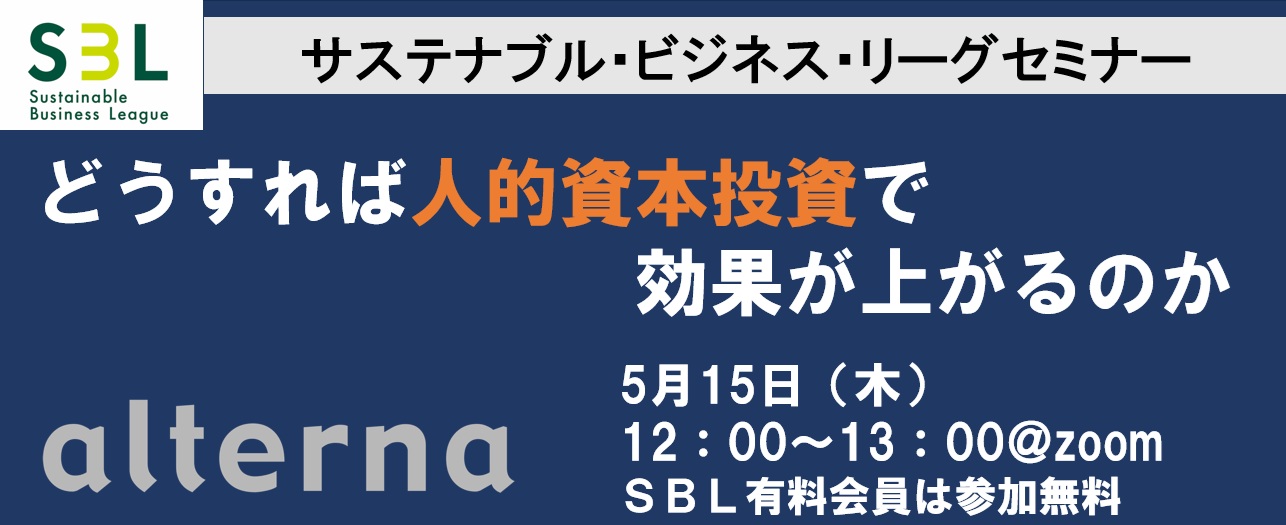


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























