「ショート・ショート」(掌小説)こころざしの譜(51)
朝のうちにブドウ木の剪定を終え、うっすらと雪を残した山の斜面を見渡すテーブルで朝刊を広げた田畑光一は思わず声をあげた。「何ですか」大輔が驚いて覗き込むと、東奥日報社会面に「横浜・山下公園でホームレス、中学生に襲撃され死亡」と大見出しが躍っている。田畑は、鴨脚勇という珍しい名前に記憶があった。鴨の脚と書いて「いちょう」と読む。葉っぱの形が似ているんで、と照れ笑いしていたあの男が殺された。
「た、た、田畑校長、今どきの中学生って、ひ、ひどいことするね」おさまっていた吃音がぶり返し、大輔は泣きべそをかいている。
「大輔、ペトロおじさんのこと、覚えているか」
「もちろん。ルミュアージュの先生だもの」

鴨脚が山あいの知的障がい者施設「Usuyuki学園」にやってきたのはもう20年以上も昔のことになる。髭を伸ばし目ぎらつかせた熊みたいな男だった。授業中の教室に突然やってきて、いきなり「ここの土地を売ってくれ。ワインぴったりの土壌なんだ」だと。なんでも、ボルドー右岸のポムロールにペトリュスという高価なワインがあり、そこのスメクタイトという黒粘土が、このあたり一帯にもあることがわかったのだとわめきたてる。
すっかり怯え切っている子どもたちがかわいそうで、田畑は怒った。
「何を勝手なことを言っているか。この学園では生きづらさを抱えた子どもたちが寄宿して、支えあって暮らしている。なんぼ金を積まれても、ここを売るつもりはない」
熊男は、80万円もするんだ、80万もと、ぶつぶつ言いながら、突然、リュックサックから何か取り出して机の上に置いた。子どもたちが遠巻きにする。それは1本のワインだった。ラベルに鍵を手にした西洋坊主が描かれており、PETRUSという赤い文字が鮮やかだ。男は器用に栓を抜くと持ち歩いているグラスにワインを注ぐと田畑に差し出した。スミレとブラックチェリーの香りが一気に教室に広がった。
「おお、芳醇で骨格がある」口に含んだ田畑がうなると、一斉に黄色い歓声があがった。男は自分もグラスを満たすとクルクルと回し鼻をぴくつかせた。
「校長、土地を売れなどと無礼な申し入れをした。済まなかった」と頭を下げた。「だが、俺はどうしてもここでワインを作りたい。どうだろう、俺を雇わないか」。
田畑は苦笑した。子供たちが小さい間はいい、しかし、成長したらどうする男は質した。仕事はあるのか、就職はできるのか。ここにブドウを植え有機栽培でワインを作ろう。土寄せ、肥料散布、剪定、除草など、収穫までにやるべき作業はいっぱいある。ブドウを摘んだ後も、醸造、樽熟成、瓶詰めと忙しい。人手はいくらあっても足りない。これから日本にもワインブームがやって来る。売れ行きがよければ卒業生を雇い、給料を払える。
男の提案は的を射ていた。田畑が長年、頭を痛めていたいことだった。
「ワインづくりを、この子たちができるだろうか」
「できるさ、気持ちがあれば。あとは経験だ」
田畑は結局、男を雇うことにした。信じられないくらいの安月給だったが。
鴨脚は見かけはぶっきらぼうでとっつきにくいが、根は純で、子供たちもすぐになついた。農業大学を出た後、ボルドーのワイナリーを転々としたというだけあってワインには詳しかった。
草むしりが得意だった冬花が「ここの土ってそんなにすごいの」と小さな声で尋ねると、
「ああ、今、冬花ちゃんが座っているその土ね、ポムロールの丘と同じ特別な粘土なんだ。乾燥期には亀裂から水分が染みこむ。逆に大雨が降ると粘土が膨張して水が下に行かないようにする。天然の水分調整機能があるんだよ」
「私の拒食症が治るようなワインだといいな。でも、こんな急斜面でも大丈夫なの」
「急斜面は大歓迎さ。ワイン造りには日照が特に重要だ。ここの斜面は南東向きで陽がよく当たるし風も通る」
「わたし絵を描くのが好きなの。ワインのラベルに使ってくれないかしら」
「いいね。有名な画家の絵をラベルに使っているワイナリーもあるからね。今度、冬花ちゃんの絵を見せて」
横から大輔が割り込む。
「ペトリュスってさあ、聖人のペテロのこと?」
「村の名前だとも石という意味だとも言うけど、大輔の言う通りかもな」
「ペトロって髭が鴨脚さんに似ているね。僕、十二人の使徒全員の名前言えるよ。だからさ、ワインのすご技教えてよ」
「いいよ。シャルドネ種の白ブドウでシャンパンを造る時だけどね。ビンを逆さにしてピュピトルという台の穴の部分に乗せ、毎日8分の1ずつ回すんだ。5、6週間かけて中の澱を一か所に集め、最後にビンから抜き取る作業がある。ルミュアージュ、動瓶というんだが、大輔、できるかな」
大輔は力強くうなずいた。
3年ほどしたころ、男に迎えが来た。「学園のワイナリーの形もできたんで家へ帰るよ」鴨脚はそう告げて去っていった。
地元の警察から、何か盗まれたものはないかと聞かれた。鴨脚は高級ワインの窃盗犯だったのだ。
それからまた何年かして、鴨脚が神妙な顔をして学園を訪ねてきた。きっと出所したのだろう。もちろん、みな大歓迎だった。
学園内にオープンしたレストランを任されている冬花が「ペトロおじさん、あなたのおかげで私たちは生きています。絵もラベルに使われています。ありがとう」皆を代表してあいさつすると鴨脚は涙を流した。
事件を伝える新聞は鴨脚のこんなエピソードを伝えていた。ホームレスをしながら、残飯漁りならぬワイン漁りが趣味だった。高級なワインの残りの香りをかぎ、味わうのが好きだった。由来は不明だが、仲間うちでは「ソムリエ・ペトロ」と呼ばれていた。
田畑は合掌し、確かにあの男は聖人かもしれないと思った。その時、冬花が駆けてきた。
「校長先生、大輔、聞いて。いいニュースよ。来月、日本で開かれるサミットのパーティーに大輔のシャンパンUsuyukiが使われることが決まったの。サミットの乾杯よ」 (完)



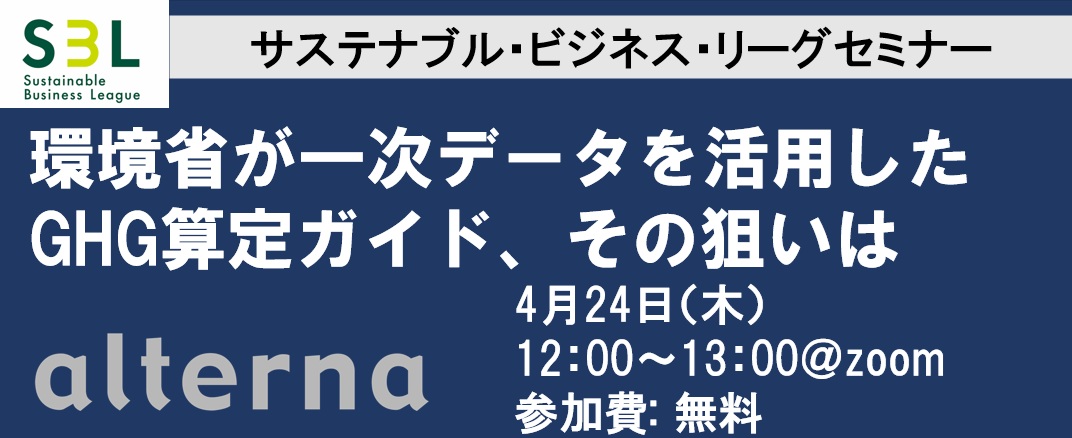

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























