■小売の取り組みが普及のカギ
あらかじめ加工されているMSC商品は、比較的流通しやすい。問題は、店舗でカットやパック詰めが必要な商品である。管理を徹底するため、加工・小売業者にも「MSC-COC認証」(以下、COC認証)の取得が求められるからだ。
国内でも加工については既に49社がCOC認証を取得しているが、小売業による取得は大手スーパーの「イオン」と「しずてつストア」(静岡県)の2例にとどまる。明神社長は「COC認証がないと真空パックに入ったカツオのたたきを、袋から出して切りMSCラベル付きで売ることはできない。販売側の取り組みが進んで店頭に並ぶMSCラベルが増えなければ、認知度も上がらない」と言う。
MSCジャパンの石井幸造プログラムディレクターも、「日本の消費者は刺身など魚の生食を好むので、新鮮な魚を店でさばくことが多い。缶詰めや冷凍品など加工済みの水産製品が多い欧州とは、やや事情が異なる」と指摘する。店頭にMSCラベルを増やすカギはCOC認証にありそうだ。
■消費者の購買行動が漁業を変える

イオンでは、鮮魚売り場の一角にMSCラベル付きのアラスカ産サケやいくらなどを集め「海のエコラベル」と大きく表示し、MSC認証の説明も添えている。統計はまだないが、消費者からは好意的な声が届いているという。その声に購買行動が伴うようになれば、環境負荷の少ない漁業が栄え、海の生物多様性の保全につながる。
世界のMSC認証漁業の数は100を超え、MSCラベル付き製品も11月に7000点に達した。普及は特に欧州進んでいる。英国では5人に1人がMSCラベルを認識しているという調査報告もある。
国際市場ではMSCラベル付きでないと売りにくい地域もあるという。日本で3番目の取得を目指して現在審査中の北海道漁業協同組合のホタテガイ漁業も、海外への拡販を見込んでいる。
MSC認証が欧州、米国から広がりつつある今、世界でも有数の水産物消費国である日本も、持続可能な漁業に無関心ではいられないだろう。(オルタナ編集部=瀬戸内千代)2010年12月17日



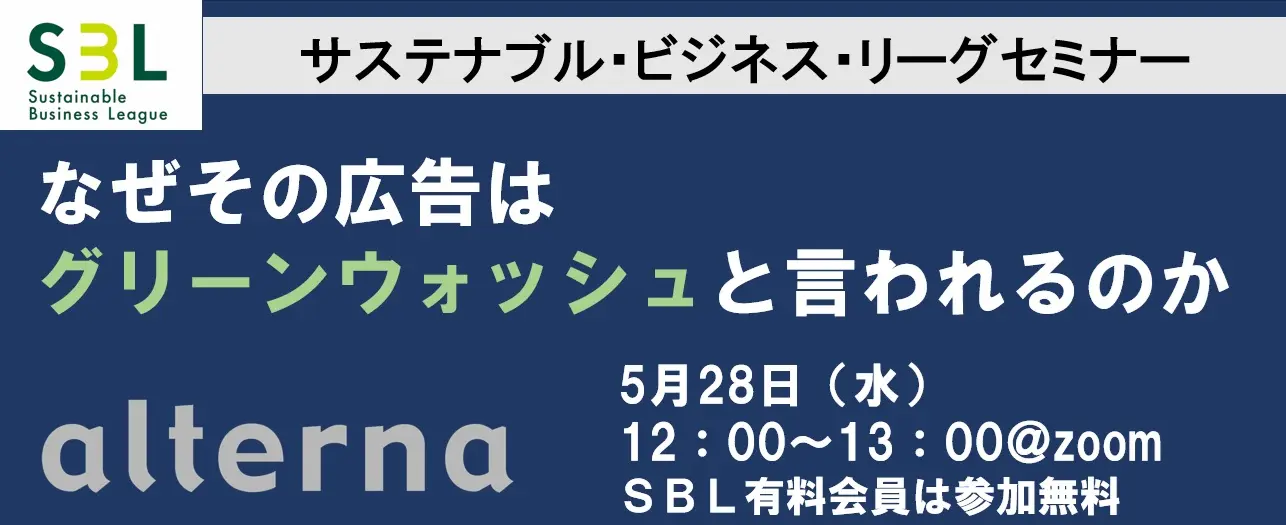


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























