日産自動車は7月30日、サステナビリティセミナーを開いた。同社では2050年までにLCA(ライフサイクルアセスメント:資源の採取から生産、流通、廃棄まで)全体でのカーボンニュートラルを目指しており、2030年代初頭には主要市場で販売するすべての新型車を電動車に切り替える。7月には、英・サンダーランド市にある自動車工場を10億ポンド掛けて、グリーン化した。ゼロ・エミッションを目指した世界初の電気自動車生産拠点に変えた。(オルタナS編集長=池田 真隆)
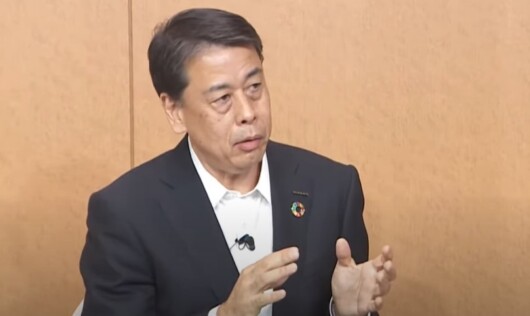
昨年末に発売10周年を迎えた電気自動車「日産リーフ」のグローバルでの累計販売台数は50万台を超えた。日産のサステナビリティ戦略はこのリーフの販売実績や開発ノウハウ、安全性能をもとに構築されている。
21年3月までに52.4万台のリーフを販売しているが、バッテリーに起因した重大事故は1件も起こしていない。安全性能と同時にバッテリー技術の革新も進めており、希少金属であるコバルトの使用量を抑えたバッテリー材料や全固体電池などの開発を強化する。
中長期的な目標として、2050年までに資源採取から原料調達、製品生産、流通、廃棄まで一台のクルマにかかるライフサイクルアセスメント全体でカーボンニュートラルを目指す。この目標の一環として、2030年代初頭には主要市場で販売するすべての新型車を電動車に切り替える。
今年7月には世界初となる「ゼロ・エミッション生産」を目指した電気自動車の生産拠点を英国に構えた。電気自動車は走行時で比べるとガソリン車よりもCO2の排出量は低いが、製造時には大量のエネルギーを使うためCO2排出量はガソリン車よりも多いことがある。
日産ではLCAでのカーボンニュートラルを目指すため、サンダーランド市に持っていた自動車工場に20メガワット級の太陽光発電装置を導入すると7月1日に発表した。これにより、欧州で販売するリーフの生産時の電力をすべて再生可能エネルギーで賄うことができるという。
サーキュラーエコノミーにも力を入れる。2022年度までに台当たりの新規採掘資源の使用量を70%に減らし、使用済みバッテリーの二次利用を増やしていく。
EVは「走る蓄電池」とも呼ばれる。リーフの大容量リチウムイオンバッテリーの性能を生かして、各自治体と組んでレジリエントなまちづくりにも取り組む。これは「ブルー・スイッチ」というプロジェクトで、自治体と有事の際に非常用電源としてリーフを活用する災害連携協定を結んだ。協定を結んだ自治体数は100を超える。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























