■【連載】政策起業家とは何者か(12)
前回に続き、「政策起業」と「ロビイング」の違いについて説明します。前回はロビイングの歴史を振り返りました。利益だけを追求した「旧ロビー活動」には1980年頃から批判が強まり、その流れを受けて公益性を持った「新ロビー活動」が生まれました。ただし、この「新ロビー活動」も政策起業とは大きく異なる点があります。(三井 俊介・NPO法人SET理事長)
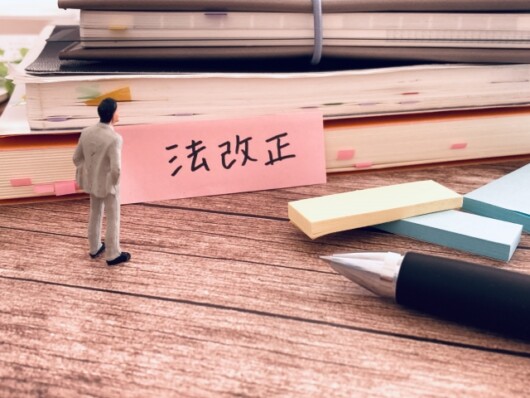
いくつかの書籍では、公益を目指すのが「新ロビー活動」だと書かれています。しかし、その定義や事例を見ると、出発点はあくまで「利益」です。公益性がないわけではないのですが、「公益」という視点を持つに留まるように見えます。
ここが、政策起業との大きな違いです。政策起業の出発点は社会課題です。さらに、新ロビー活動よりも公益性の色合いが強いです。
「新ロビー活動」について詳しく見ていきます。まず定義は次の通りです。「政策アクター(政治家・官僚)の政策決定・執行に何らかの影響を与えるために行われる利益団体の意図的活動全て」「利益団体は『国に政策アクターから有利な政策を引き出し確保し、自己利益を守るため』にロビイングを行う」。
企業を例に考えると、競争上の優位性の獲得または不利な状況の回避を目的に行うことが分かります。新ロビー活動では、「特定の法案ないし法律に関して、社会一般の人々に対して働きかけること」が重要とされます。
具体的にはデモや署名活動などです。これらを「草の根ロビイング」または「間接ロビイング」と呼びます。
「草の根ロビイング」で行う政策実現の手法は下記の通りです。
「課題だと思うことを発信し、仲間を募る」「役所に行き、解決までのステップを確認する」「議員に会いにいく」「陳情・請願などを行う」「メディアに報道してもらう」「委員会・審議会に入る」「モデルとなる事業をやってみる」
まとめると、新ロビー活動は公益性は伴ってはいますが、あくまで利益を出発点としたものです。一方、社会課題を起点にする政策起業は公益性の度合いが強いです。
しかし、この「公益性」を定義することが非常に難しいことも事実です。次回は「公益」とは何かについて書きます。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























