■オルタナ70号第一特集先出し記事「外形のガバナンス/内面のガバナンス」
■記事のポイント
①企業のガバナンス向上には、ダイバーシティ(多様性)がカギに
②投資家に対して、ガバナンスの情報をどう開示するか工夫も必要
③ガバナンス向上に欠かせないポイントをESGの専門家3名が語る
ESG投資が広がる中、国内企業にガバナンスは本当に根付いたのか。ガバナンスを機能させるには何が必要なのか。運用機関のESG担当者、ESGコンサルティング会社パートナー、大手メーカーのESG担当者の3人に語ってもらった。(オルタナ編集部)

■ガバナンス推進ミドルにも責任
─ガバナンスとは何かを考える時に、誰が司るのかが重要ですね。
A:課長や部長など中間管理職と、執行役員クラスだと思います。理想的には全従業員ですが、自分の出世だけを考えるのでなく、会社を良くしていこうという意識が管理職以上に染み入るのが大事です。
B:ガバナンスの定義にもよりますが、コーポレート全体のガバナンスという観点からは長期的視点でマネジメントできる人が、ガバナンスを司る必要があると考えます。執行側はどうしても短期目線で、自分たちの成績に一喜一憂しがちです。
C:ガバナンスが日々の繰り返しの中で効いてくるものと考えるなら、司るべきはミドル層です。仕事の最前線で責任を持って意思決定するミドル層がおかしくなると不祥事も起きます。ミドルからのアップダウンでガバナンスを機能させる必要があります。
─ガバナンスの推進に必要なことは何でしょうか。
C:社内の多様性が前提です。当社の社内分析では、女性管理職の比率が高い部署ほど、ガバナンスや企業倫理に対する満足度が高いことが分かりました。多様性があれば、一つの方向に流れない反作用が働き、組織の活性化につながります。
─「女性管理職が何人」といった外形だけでなく、内面を追求することが大切です。
B:本来は「女性だから」「男性だから」ということよりも、自社の戦略に合わせて、個々の能力やパーソナリティ、経験の多様性で選ばれるべきですね。
しかし現状を踏まえると、まずは外形から入る、つまり女性の比率を増やすのが先決だと思います。そもそも、女性は同じ土俵に上がるチャンスが乏しかったのですから。
女性ではありませんが、ヤマハは以前、社外取締役にウォルト・ディズニー・ジャパンの元社長を選任しました。当時の中期経営計画ではブランド強化が謳われており、会社が今後どういう方向を目指すのかという戦略の視点から選んだのでしょう。
■世界の市場は多様性が前提に
A:企業価値創造モデルの実行に際して、国内企業は内輪の論理に入りがちです。暗黙知のようなものがあり、本来見つめ直すべきものが見つめられないのです。
それを避けるには、性別だけではなく国籍、年齢などあらゆる多様性を取り入れるべきです。特に海外で事業展開している企業は、その国や地域の人を採用することが大切です。
C:当社は現在、従業員の半分以上を外国人が占め、売り上げの多くが海外です。事業のスピード感の違いなどを巡って時に衝突も起きますが、だからこそ組織が活性化するのです。
顧客のニーズが多様化する中、企業も多様な価値観を持っていないと社会の変化に対応できない時代になりましたね。
─男女雇用機会均等法の施行から40年近く経ちましたが、まだプロパーの女性役員は少ない。一方、女性たちが上の世代の大変さを見てきて、役員を目指さないという見方もあります。
C:そもそもなぜ大変と思うのか、背景を理解することが大事です。子育てが女性中心の社会システムを見直したり、女性が活躍するには家庭でのパートナーの理解が必要だったりする文化を変えるべきという意見もあります。
A:根深いのは学校教育です。学級委員長は男子で副委員長は女子というのが長い間の定番で、会社に入ってからも管理職に向けた研修は、専業主婦がいる男性をイメージした内容が多いです。
最近では、ダイバーシティ(多様性)・エクイティ(公平さ)&インクルージョン(包摂)といわれるようになりました。エクイティは、ハンディキャップに考慮して、多少は下駄をはかせないと実現できません。数合わせではなく、本当に解決する意志があるのかが、最大のポイントです。
実際にそれができている企業もあります。例えばリクルートは、男女雇用機会均等法の前から男女平等が根付いていました。リクルートホールディングスは会長が50代、社長が40代という若さも特徴です。
B:他の国内企業も、女性が活躍しやすい環境をつくろうと動き始めています。これまでは、能力があっても環境のせいで諦めていた人もいました。意欲がある人が意欲をなくすことは良くないです。
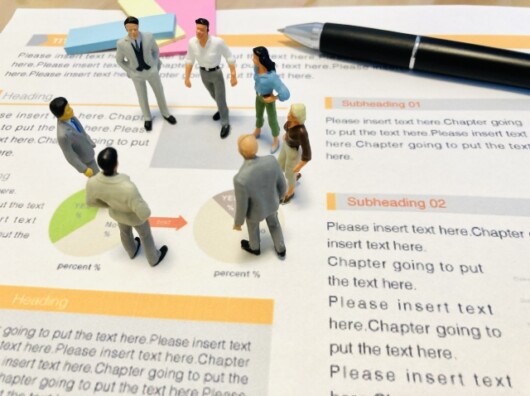
─こうなると、教育や政治の問題になりますね。日本はジェンダーギャップ指数が116位で、日本社会全体の変容が必要です。どう改善できるでしょうか。
A:政治に期待するのは、難しいです。グローバル企業は国内よりも国外に目線を置いています。こうした企業は日本社会のあり方に関係なく、ガバナンスの体制を整えて前進していきます。
企業経営者やI R担当者は「ヘッドライン(報道)リスク」を気にする人が多いですが、長期的な戦略に基づいているならそれほど気にすることはないです。
B:近年は投資家だけでなく、他のステークホルダーの意識も高まってきていると思います。環境や社会に関心が高いステークホルダーの声に真摯に耳を傾けていけば、必然的にガバナンス強化になるでしょう。
■プライム市場の社数は多過ぎる
─2006年にPRI(国連責任投資原則)が生まれ、ESGの概念が広がりました。それ以降、企業のガバナンスは進化したと思いますか。
A:進化しましたね。最初は「社外取締役などお飾りにすぎない」という認識が大部分でした。そこから取り組みを始めて、社外の声を入れることでガバナンスを効かせ、時価総額が上がった企業も増えました。
ところで現在のプライム市場ですが、1800社は多すぎます。これは最大の愚策です。学校なら、公立高校全体の成績を上げるようなもので、選択と集中ができていません。進学校に当たる上位300〜500社に絞って価値を上げていけば、海外からの評価はもっと高まったはずです。
C:機関投資家や事業会社40社以上にインタビューする機会があったのですが、「ガバナンスが効いている企業」と「そうでない企業」の二極化が進んでいるという声が多く上がりました。
これ以上二極化を広げないために、全体のレベルを上げないと。日本は約700社が統合報告書を出しているので、まずここを底上げすることが先決でしょう。
B:私も進化したと思います。両極化の話が出ましたが、「ガバナンスが効いている企業」では、経営者が独りよがりにならないように社外取締役を選んで、発言に対して真剣に耳を傾けており、良い緊張感が生まれていると思います。
こうして取締役会が機能している企業は総じて統合報告書の完成度が高く、価値創造ストーリーも描けていると感じます。
■米欧の企業は説明が得意
─ガバナンスが機能している企業の利益が高く、価値創造ができ、時価総額も増えていく。この公式が浸透していけば、それに追随せざるを得ないでしょう。





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























