■日本の自然を理解した「日本のプランB」を
――低エネルギー社会の具体的なイメージはどんなものか
別に江戸時代に戻れ、と言うことではない。まずは日本の自然の特徴を徹底して理解する必要がある。自然エネルギーは濃縮されずに遍在しているので、濃縮にエネルギーを使わずに「おらが村のバイオマス発電」「おらが村の風力、水力発電」というように、地域ごとに適した自然エネルギーを地域で使用することが大事だ。
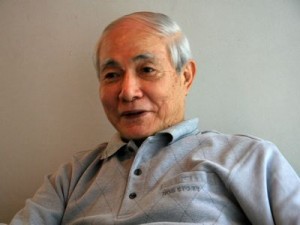
中世からの歴史を誇るオランダの木製風車が有名だが、これが優れているのはオランダ人が北海、陸、バルト海と、風の通り道をよく理解し、風力を機械エネルギーのまま粉ひきや鍛冶などの動力として利用した点だ。電気に変換していないので、むしろエネルギー利用効率はよかった。
自然エネルギーというとすぐに蓄電池に充電を、とか考えがちだが、そうしてエネルギーを濃縮するプロセス、システムが大きくなればなるほど、そのためにエネルギーを消費し、効率は落ちる。小水力発電も別にダムをつくる必要はなく、2~3メートル程度の落差で水車を回せば便利で効率もよい。
交通や物流でも、現在のクルマ偏重ではなく、地域内では自転車やLRT(次世代路面電車)やコミュニティバスの活用、地域間では世界第6位の長さを誇る海岸線を利用した舟運、海運を進めるべきだ。欧州など大陸の真似をしても決してうまくいかない。私が提唱する「日本のプランB」とはそうした内容だが、まず浪費しない、無駄をしない、もったいないと思う社会を目指すことだ。
――自然エネルギーの普及という点では発送電分離も焦点だが
地域分散型の自然エネルギーの普及には、発送電分離が絶対に必要だ。現在の電力独占体制では、低エネルギー社会の実現は難しい。利権でつながり、司法も加担する政・官・財・学の癒着が原発安全神話を生んだ。それが福島第一原発事故となったのだ。
(聞き手:オルタナ編集長=森摂、斉藤円華)






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























