■小林光のエコめがね(24)■
2021年末に上梓した『GREEN BUSINESS環境をよくして稼ぐ。その発想とスキル』(木楽舎)は、お陰様でこの1年間で、初版3000部に対して2130部を買い上げていただいたと聞いた。
お堅いテーマなので、すぐには売れなくとも、中身が古くならないように考えて本を編んだ。つまり、目先の出来事を追って解説するのではなく、むしろ、出来事の背景にある考え方などを説明し、身に着けていただくように気を付けて執筆、編集した。しかし、思った以上の速い売れ行きだ、と感じている。
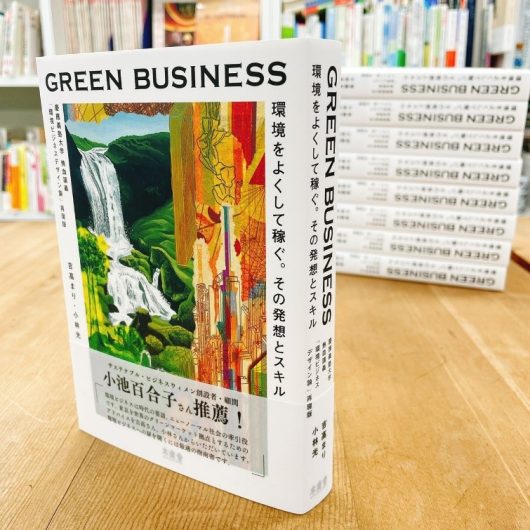
その背景には、環境をよくすることが、ビジネスにとってのマテリアリティにしっかりとなってきたことがあるのだろうと思う。
11月8日付けの本欄で紹介させていただいた「実践環境ビジネス」は、社会人向けの演習であって、参加者に環境ビジネスのリアリティを感じ取っていただくことができたと思う。そのほかにも、本書の著者、吉高まり氏と私とで参加者にインタラクティブな形で環境ビジネスの勘所を直接に伝えるべく取り組んでいることもある。
それは、本書の母体となった、通算12年目に入った、慶應義塾のSFCキャンパスの大学院での「環境ビジネスデザイン論」の授業であり、2022年から始まった東大・駒場の「グリーンビジネス方法論」の授業である。

写真は、その東大・駒場の授業の様子。実質14コマのうち、4コマで、リソースパーソンとして実際に環境ビジネスに取り組んでいる経営レベルの方をお招きし、学生とのディスカッション、そして、学生側からのビジネス発展に関する提案発表という仕掛けを繰り返して進む。いわゆるアクティブ・ラーニング式の授業である。
東大なので、来ていただく方には、東大の卒業生がなるべくいらしてくださるように配慮しているが、来校した先輩ビジネスパーソンから、「在学中にはなかったタイプの授業で、こうしたものが当時からあったら良かった」「現役の在校生をうらやましく思う」などと感想を言ってもらえている。こちらとしても教員冥利に尽きる。
来校のリソースパーソンに私から特に要望しているのは、困難を突破してきた成功談も良いが、今直面している課題や苦しみ、悩みこそ共有していただきたい、ということである。悩みを聞けば、先輩との閾が低くなり、在校生もいっぺんに自分事として考えることができる。ミラーニューロン・システムのなせる業だろうか。
社会人相手に、もっぱらケーススタディだけをする場も主宰している。これまた10年以上続いているCSV経営サロン(大丸有地区の「エコッツエリア」)である。ここでも、かつては、成功の秘訣を学んでいたが、今は、乗り越えるべき課題や解決策を阻むものなどを聞いて、その突破策を議論するようにしている。
本では、古い情報にすぐなってしまうのでなかなかできない芸当だが、このような悩みの積極的な開示と共有が、新しいビジネスエコシステムの創出には一番の早道ではないだろうか。



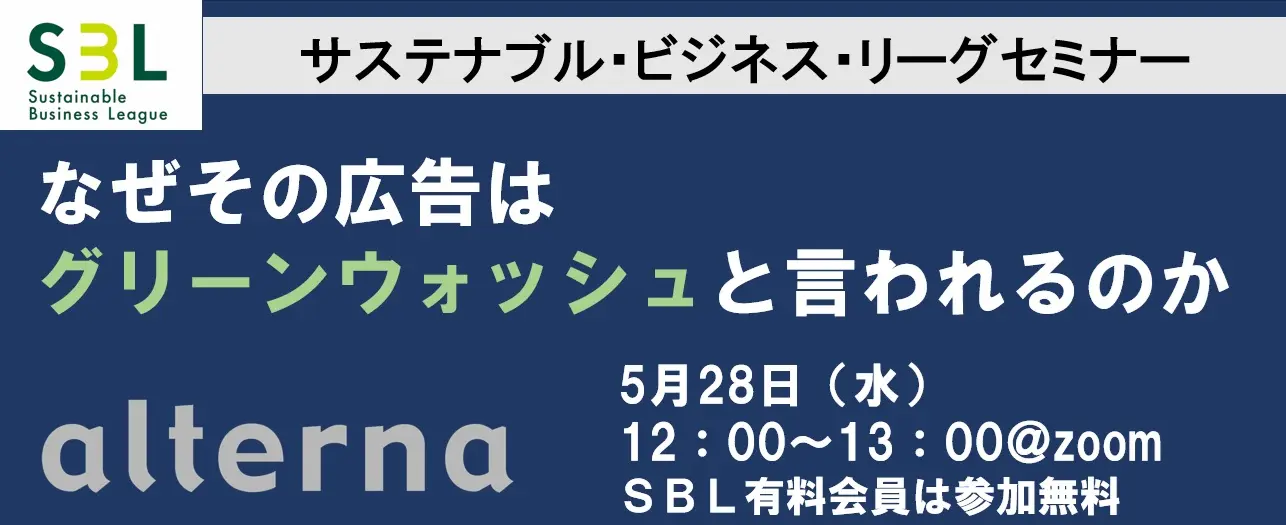


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























