
「7万人もの人がさまよっている時に、一体何をやっているのですか」。7月27日の衆議院厚生生働委員会の公聴会で、福島の原発事故をめぐる国と国会の対応を強く批判して反響を呼んだ東京大学のアイソトープ総合センター長の児玉龍彦教授が12日、記者会見を開いた。
児玉教授は放射能の測定と除染を今以上に急ぎ、かつ大規模に行うことを訴え、その上で事故に対応するための特別立法が必要であると主張した。
除染活動については、子供や妊婦など放射能の影響を受けやすいと指摘し、幼稚園などの場所で詳細な測定が必要と提言した。「各自治体に『測定すぐやる課』、問い合わせに応じるコールセンターを置き、国が詳細な汚染地図をつくり、放射線被曝の危険を減らして住民の不安を少なくすべき。雨などで汚染状況は時々刻々とかわるために、地図は常にアップデートが必要だ」と述べた。
その上で、土地の除染と内部被爆を避けるために食品の汚染検査を行うことを訴えた。「各国で放射能や有害物質の除染の経験がある。多くの日本企業は放射能の測定装置を作る技術力を持つ。しかし、そうした知恵が有効に活かされず、国の取りまとめと実施が遅れている」と批判した。
現在の放射能をめぐる法律や基準は一部の基準が突如緩和された以外は、原子力事故前のまま。実際の除染や住民の保護活動の実情にあわない場面も多いという。そのために、「測定、除染、放射性物質管理を適切に行うための特別立法を行うべきだ」と話した。
今回の原子力事故で大気中に出た放射性物質は、広島に落とされた原爆の20倍と児玉教授は試算。「とてつもない年月、費用、日本の知恵と努力を集めなければ、安全な国土は取り戻せない。何ができるのかと国民一人ひとりが考え、合意し、参加してほしい」と訴えた。
児玉教授は内科医として臨床と研究の双方に関わり、96年から東大先端科学技術研究センター教授、11年からはアイソトープ総合センター長を兼ねる。原発事故後は福島県南相馬市で放射線量の測定、除染活動を続けている。(オルタナ編集部=石井孝明)



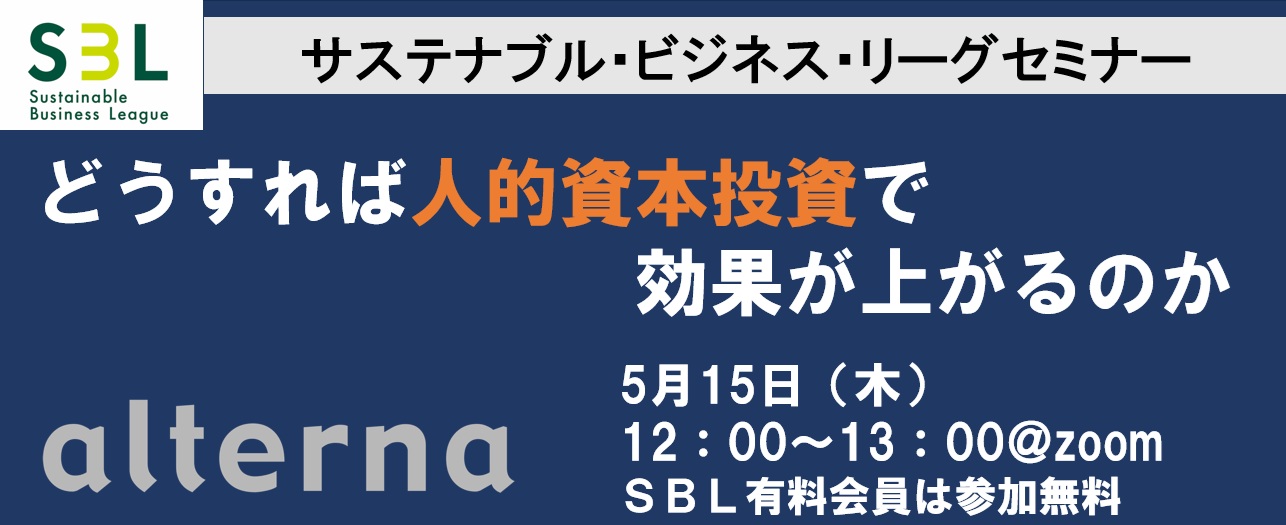


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























