記事のポイント
- 企業にネイチャーポジティブへの転換を促す共同体が発足した
- SMBC、MS&AD、日本政策投資銀行、農林中央金庫が立ち上げた
- 金融4社は連携して、企業の転換を促していく
三井住友フィナンシャルグループやMS&ADインシュアランスグループホールディングスなど金融4社はこのほど、企業にネイチャーポジティブへの転換を迫るアライアンスを立ち上げた。ネイチャーポジティブは「2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復傾向に向かわせる」という概念だ。国連が採択した生物多様性に関する長期目標の考え方の軸になっている。金融4社は連携して、企業の生物多様性への取り組みを後押ししていく。(オルタナ総研フェロー=室井孝之)
このほど立ち上がったアライアンスは、「Finance Alliance for Nature Positive Solutions(略称FANPS)。三井住友フィナンシャルグループ、MS&ADインシュアランスグループホールディングス、日本政策投資銀行、農林中央金庫の4社が立ち上げた。日本総合研究所、MS&ADインターリスク総研、日本経済研究所、農林中金総合研究所もメンバーだ。
このアライアンスの目的は、企業にネイチャーポジティブへの転換を迫る。ネイチャーポジティブとは、「2030年までに生物多様性の損失を食い止め、回復傾向に向かわせる」という概念だ。
2022年12月の国連生物多様性条約COP15で採択した、「昆明・モントリオール生物多様性枠組」でもネイチャーポジティブが取り入れらた。
TCFDの生物多様性版である「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)」は今年秋(9月)に、情報開示フレームワークを発表する予定だ。企業は気候変動だけでなく、生物多様性への対応も求められる。
一方で、自然との関わりは、場所や事業活動ごとに極めて多様だ。そこで、金融機関4社は連携して、企業のネイチャーポジティブに向けた取り組みを支援する。
FANPSの研究テーマは、「ネイチャーポジティブに資するソリューションの調査、整理」と「ネイチャーポジティブに資する事業活動への転換を支援、促進する金融の検討」の2点だ。
例としては、前者は「湿地再生や雨水浸透策による水源涵養」や「環境再生型農業による土壌環境や水環境の改善」、後者は「環境インパクトボンド」「生物多様性リンクローン」や「自然配慮評価融資」だ。



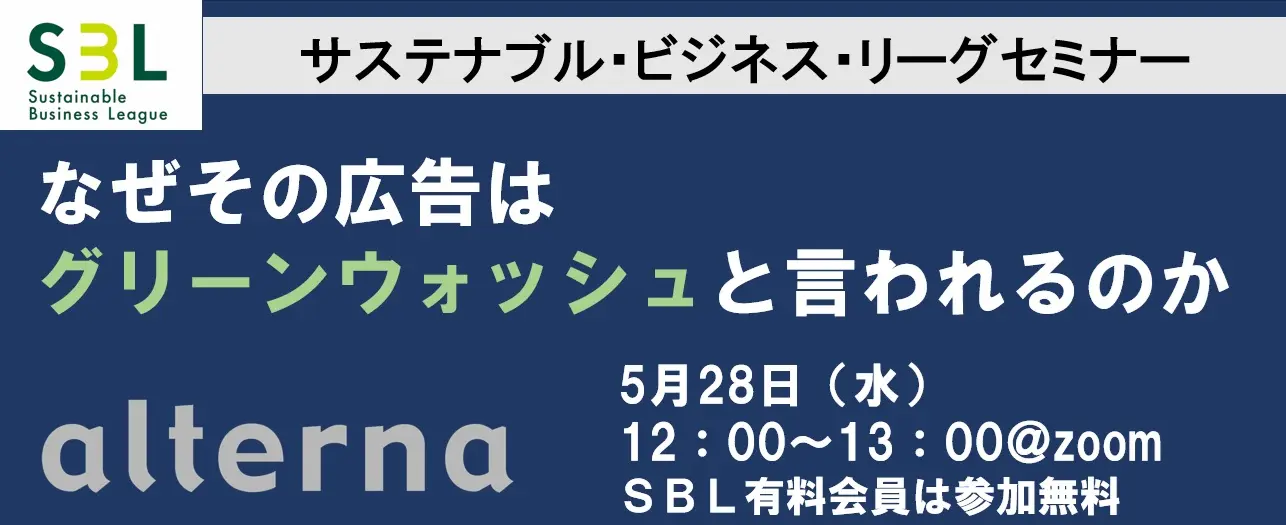


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























