9月22日に鳩山首相が国際公約した温暖化対策については、コストだけをとらえて後ろ向きに考えるのではなく、日本の経済社会が大きく変わるチャンスであり、日本の競争力を高めるための好機と考えたいものです。
その中で、最近よくマスコミで取り上げられているのが「温室効果ガス25%削減なら、可処分所得は一世帯あたり年間36万円減る」という見方です。
この数字の根拠は、麻生前政権が温室効果ガスの中期削減目標を決める際に、内閣官房の中期目標検討委員会などで出てきた資料です。
ただ、これには大きな誤解があります。
環境省の地球環境局地球温暖化対策課の担当者さんは、下記のように説明してくれました。
《「年間36万円」というのは、 2020年に温室効果ガスを25%削減した時(可処分所得予想555万円)と、削減しなかった時(可処分所得予想591万円)の差が36万円あるというだけで、「現在の可処分所得(05年、479万円)から36万円減る、というわけでは決してありません。むしろ所得は76万円増えるのです》
(別図参照:地球温暖化に関する懇談会資料などを元にオルタナ作成)
さらに環境省・担当者さんは
1)この数字にはグリーンニューディールなど、温暖化対策のプラス効果が入っていない
2)高波や旱ばつ、マラリアなど温暖化対策を取らなかった時の被害コストが入っていない
――などの指摘をしていました。つまり、温暖化対策によるコスト(光熱費の増加など)だけを捉えて、しかも、現在より36万円も可処分所得が減るかのような誤った見方や報道は、かなり問題があるというのです。
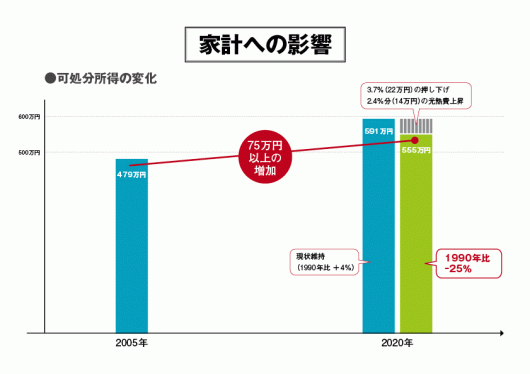
また、25%削減のために今後導入されるであろう、環境税(炭素税)は、これまでの議論では「税収中立」(納税者の負担は変わらない税制)です。環境税としての税収を年金財源に充てているドイツなどがお手本です。つまり、環境税税が導入されたからといって、そのまま可処分所得が減る、という論理は成り立ちません。
つまり、結論的には、「年間36万円」という数字自体が、かなり怪しい存在であることが分かります。グリーンニューディールで経済が活性化すれば、GDPや可処分所得は上向くはずですし、何より国民負担は、今後の温暖化対策の設計次第で大きく変わります。CO2削減で頑張った人は報われ、頑張らない人は多くを払う仕組みが必要なのは言うまでもありません。
このメールを読まれている賢明な読者様は、「温暖化対策を進めると家計に大きく響く」――という誤解をされないことをお勧めいたします。
環境問題は、このように、変な数字の一人歩きや、誤解、風説が本当に多い分野です。オルタナも気をつけたいところです。






-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























