記事のポイント
- 良品計画が、店舗で回収した衣服をアップサイクルする「ReMUJI」事業が順調だ
- 販売点数は21年度に7倍に伸び、取扱店舗も全国22店舗に拡大した
- 地域密着の店舗経営で、取り組みに共感する顧客が増え、回収量が拡大した
良品計画が回収した衣服をアップサイクルして販売する「ReMUJI」事業が順調に推移している。今年8月現在、アップサイクル商品「ReMUJI」の取扱店舗は全国22店舗に拡大した。店舗で回収した同社製衣服を、染め・洗い直したり、つないだりして再生した一点ものの商品が生活者の支持を集めた。(オルタナ編集部・北村佳代子)

良品計画は今年、アップサイクル商品「ReMUJI」の販売店舗を、これまでの全国5店舗から全国22店舗へと拡大した。
「ReMUJI」は、着なくなったMUJIの衣服を全国の店舗で回収し、「洗い直した服」「染め直した服」「つながる服」として、一点ものの付加価値をつけて売り出したアップサイクル商品だ。
自社の衣服を資源として循環させる「ReMUJI」の取り組みは、その素材となる回収した衣服がなければ成り立たない。衣服の回収量が増えたことで、「ReMUJI」の展開が加速した。
■資源循環を進める大前提は、回収が根付くこと

「ReMUJI」事業を推進する良品計画の産地開発部・素材開発担当の戸村幸太氏は、「循環をつくるためには、まず回収が根付く必要がある」という。同社は2010年に衣服回収を開始したが、「ReMUJI」のプロジェクト立ち上げまでには5年を要した。
「当初の衣服回収の目的は、リサイクルしてエネルギーに転換することでした。店頭で回収が始まると、かなりきれいな状態で衣服が戻ってくる。これらをリサイクルに回すのはもったいないと考え、リユースに向けた議論を重ね、『ReMUJI』が生まれた」(戸村氏)
■販売数は約4000着から7倍の28000着に

「ReMUJI」拡大のターニングポイントとなったのが、2021年9月のMUJI新宿店のリニューアルだ。「ReMUJI」を前面に打ち出し、「染め直した服」に加え、「洗い直した服」「つながる服」も仲間入りした。
お客様に「ReMUJI」の取り組みが、より可視化できるよう、全国の店舗でも、回収ボックスをわかりやすい場所に設置した。「ReMUJI」を販売する店舗では、お客様に循環を身近に感じてもらえるよう、「ReMUJI」売場のすぐ隣に回収ボックスを配置するなどの工夫をした。
2022年8月期の「ReMUJI」販売数は、前期の3927着の7倍を上回る28222着となった。
■仕分け作業の負担軽減に取り組む
衣服の回収を担う、店舗の負担を軽減する取り組みも進む。
回収後の衣服をリユースに回すのか、リサイクルに回すのかの判断も含め、仕分け作業の一部を担うのは現場の店舗だ。
「回収量が増えるだけでも仕分け作業は大変だが、素材の混率の確認など、回収後に店舗で行う仕分けオペレーションのフローが難しかった」
実店舗で店長も経験した戸村氏は、かつての現場の苦労を振り返る。
「資源循環という良いことをしているのに、それが大変になってしまうと長続きしない。回収の後工程の負担を軽減しようと、より容易に仕分けができるよう、マニュアル整備を進めた」(戸村氏)
■課題は「大きめ衣服の回収」と「季節の逆転」
「当社のコアの顧客層は、30代、40代の女性が多い。MUJIのファンとなったお客様が、喜んで『ReMUJI』を買ってくださっている」と戸村氏は言う。
課題は、男性用衣服の回収だ。
「『ReMUJI』の色味や、古着のような見た目から、若い男性からの問い合わせも多い。しかし、女性用衣服に比べると、男性用衣服の持ち込みが少ないため、『ReMUJI』は大きめサイズの品ぞろえが少ない」という。
季節の逆転現象も課題だ。衣服が回収されてから、「ReMUJI」となって店頭に戻るまで、最短でも2か月かかる。衣服の回収量は衣替えシーズンに増えるため、「ReMUJI」として店頭に出すときには季節外れになってしまう。
■古くから店舗がある地域ほど、衣服の回収量が多い
良品計画は2023年5月末現在、日本全国に555の店舗を構える。
「古くから店舗がある地域ほど、衣服の回収量も多い。きれいな服も多く、大切に着てくださっていたことが伝わる」と戸村氏はいう。
店舗を拡大し顧客が増えても、回収量を増やすには、顧客側に、着なくなった服の中からMUJIだけを仕分け、持ち込んでもらうひと手間のアクションも必要となる。
無印良品は、「これがいい」より「これでいい」という理性的な満足感をお客様に持ってもらうことを目指してきた。店舗経営では、生活圏での個店経営を軸に、地域に密着する「土着化」を大切にしてきた。
衣服の回収が進んだ背景には、同社のこうした企業姿勢に対する顧客の共感もある。
■誰もが気軽に、気負わず、参加できる循環を
良品計画・広報課の関根純子氏は「ReMUJI」の取り組みについて、「誰もが資源循環に、気軽に、気負わず、参加できるようにしたい」と話す。
「取扱店舗が増えたといっても、まだ全国約500店舗の22店舗でしかない。当面の目標は、より多くの地域の方に、『ReMUJI』を手に取っていただける環境にしていくことだ。お客様の中で循環の取り組みが広がることで、地域全体の循環にも波及すると良いなと思う」(戸村氏)
「まずは、『ReMUJI』の風合いを手に取って見ていただきたい。環境に良いことをしようという気持ちでなく、単純にファッションとして、一点ものの古着を探す醍醐味を楽しみ、着ていただけたら嬉しい」(戸村氏)



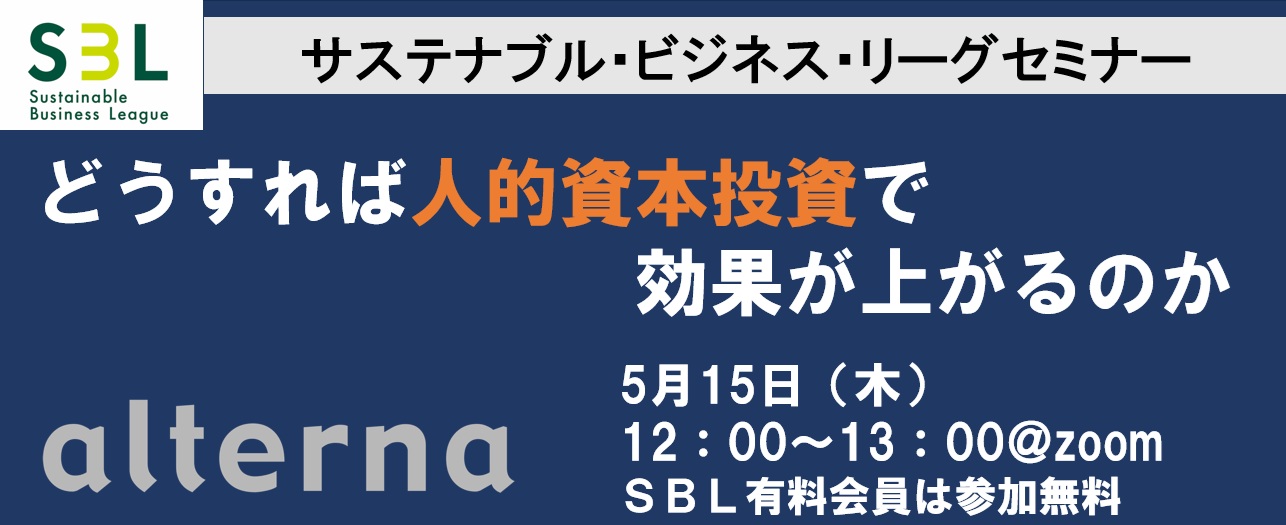
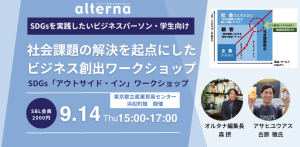


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























