記事のポイント
- 公海の生物多様性保護を目的とした協定に67カ国が署名した
- 初めて「公海」における生物多様性保護に言及した協定だ
- 漁業禁止区域も設定し、公海での活動が環境影響評価の対象になる
国連はこのほど、公海の生物多様性保護を目的とした「国家管轄権外区域における海洋生物多様性協定」に67カ国が署名したと発表した。初めて「公海」における生物多様性保護に言及した協定だ。日本政府は現時点で署名していない。(オルタナ編集部・下村つぐみ)

どこの国にも属さない「公海」は、これまで海洋保護の対象外になっていた。米ナショナルジオグラフィックは2023年3月、保護されている公海は全体の約1%に過ぎず、公海上ではいまだ密漁や人身取引などが横行していると報道した。
国連は6月19日、「国家管轄権外区域における海洋生物多様性協定」(BBNJ)を採択した。公海の環境保護と生物多様性保護を目的とした法的拘束力をもつ協定だ。発効すれば、漁業禁止区域などが設定され、公海での活動が環境影響評価の対象になる。
批准の前段階として、各国が同協定への批准の意思を示す署名がある。国連本部(本部:米ニューヨーク)は2023年9月20日に署名の受付を開始した。期間は2年間だ。署名を開始してすぐに67カ国が署名した。
署名後、同協定を遵守するために必要な国内の法律・制令を整えた国から順次批准し、60カ国が批准した段階で同協定は発効される。
10月6日時点で、日本政府は署名していない。
この協定では主に以下の4つを定めている。
1、海洋遺伝資源の取り扱いや利益配分
2、(海洋保護区を含む)区域型管理ツールのような措置
3、公海における環境影響評価
4、開発途上国への能力構築及び海洋技術移転
海洋遺伝資源は製薬などに活用される貴重なデータとして、誰でもアクセスできるデータベースで管理し、IDで追跡する。魚などの海洋生物資源は海洋遺伝資源の対象外だ。
この海洋遺伝資源から生じた利益の一部や、締約した先進国が毎年課せられる特別基金への拠出金は、開発途上国の能力構築や海洋技術の支援に充てられる。先進国による拠出金は、同協定で設置される締約国会議(COP)が決定するまで継続しなければならない。
先進国の負担は大きいものの、2030年までに世界の陸・海における生物多様性を30%保全する「30by30」の達成に向けて、大きな一歩となる。



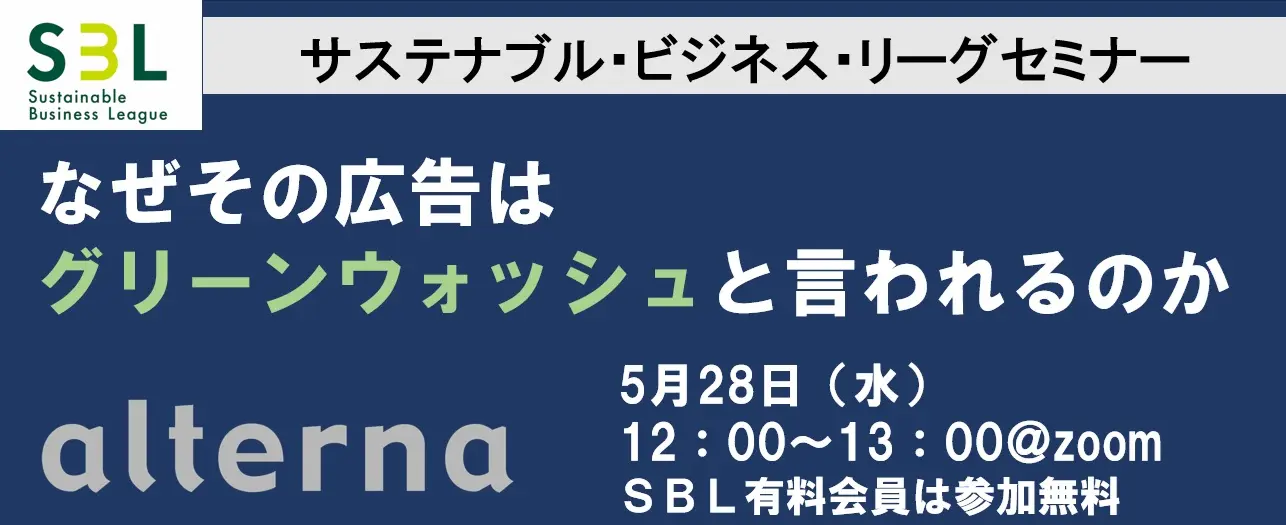


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























