記事のポイント
- シーフードレガシーなどが第5回サステナブルシーフードアワードを開催した
- 北三陸ファクトリーと愛知県立三谷水産高等学校の活動が大賞に輝いた
- 磯焼けが生んだ痩せウニを再生・商品化し、磯焼け防止活動をビジネス化した
日本の水産業のサステナビリティに貢献したプロジェクトを表彰する「第5回サステナブルシーフードアワード」が10月17日に開かれた。北三陸ファクトリー(岩手県洋野町)と、三谷水産高等学校(愛知県蒲郡市)が大賞に輝いた。北三陸ファクトリーは、磯焼けで痩せてしまったウニを再生して商品化し、磯焼け防止活動をビジネスにした。(オルタナ編集部・下村つぐみ)

サステナブルシーフードアワードは2019年に始まり、今年で5回目を迎えた。
3部門9組のファイナリストのうち、水産業を営む北三陸ファクトリーの「ウニ再生養殖」と愛知県立三谷水産高等学校の「未利用資源活用による担い手育成」が大賞に輝いた。
北三陸ファクトリーは、岩手県の沿岸最北端に位置する洋野町を拠点に、磯焼けで痩せてしまったウニを再び育て、商品化する「ウニ再生養殖」を展開する。
その養殖場「ウニ牧場」は、北から南に約18キロも広がる溝で、沖から流れてきた天然の海藻や昆布が繁茂する場所だ。漁師たちが約55年前に、海岸沿いの岩盤を掘ったことが始まりだという。
全国各地で問題になっている磯焼けは、ウニや巻き貝が海藻を過剰に食べることが大きな原因だ。海藻が減少した海域で育つウニは、中身がない痩せウニとなり、廃棄されることが多い。
同社は、磯焼けが起こる地域からウニを漁獲し、天然の海藻や昆布が繁茂したウニ牧場でもう一度ウニを育て直す。磯焼けを防止するとともに、再生したウニを販売し、ビジネス化した。
短期間で実入りのウニに改善させる飼料やウニを海面で養殖するためのカゴは、北海道大学などと共に開発した。
2022年度には3106.5トンのCO2を吸収し、「ブルーカーボン」としてJブルークレジット認証も取得した。
三谷水産高等学校では、10年ほど前から企業と協同して、未利用資源の商品化を進めてきた。
2023年度は、地元の老舗練り物屋であるヤマサちくわとともに、深海のエビ「ジンケンエビ」を使用したチヂミ風薩摩揚げを考案した。ジンゲンエビは5センチほどの大きさで、殻剥きに手間がかかるという理由から廃棄されていたという。
10月28、29日には、JR名古屋の高島屋で冷凍販売を行う予定だ。
登壇した同校の水産食品科3年の伊藤海さんは、ヤマサちくわに来年就職する予定だ。地元企業との連携や6次産業化の推進が担い手の育成につながっている。
このほか、特別賞には、消費者から注文の入った魚だけを獲る「受注漁」を行う邦美丸の富永さん夫婦が選ばれた。



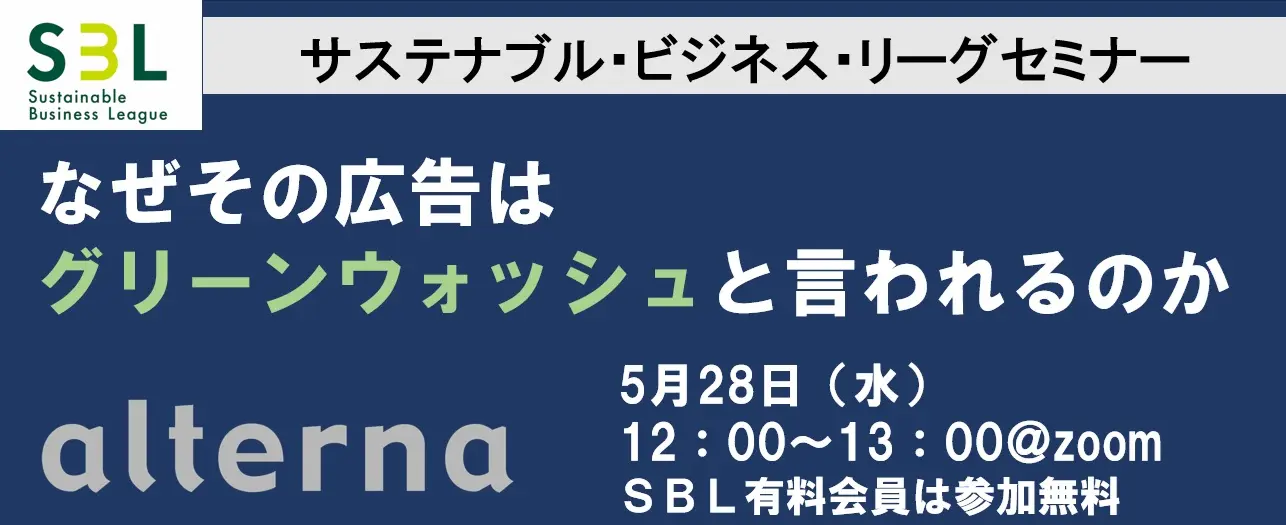


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























