
オルタナは9月26日、「脱・横並びのCSRレポート」セミナーを開いた。講師として出席した伊藤園の笹谷秀光・常務執行役員CSR推進部長は、「CSRレポートを読んでもらうにはストーリー立て」を強調した。笹谷常務執行役員の発言要旨は次の通り。(オルタナ経営企画室=佐藤 綾子)
・私が伊藤園CSR推進部長に就任した2011年、「CSRレポート」を作るに当たって、GRIの準拠とESG、統合報告ととても難しいことをやらなければならないと覚悟したが、ISO26000を学んで、従来のCSRレポートの発行体制を大幅に見直した。とにかく読みごたえのあるものを作りたいという思いが強かった。
・ISO26000の中核主題は、ほぼ全ての部署に関連しているので、組織を横断する社長直轄の組織・CSR推進委員会を設立した。この組織は部長級からなり、年に6回、有識者を招いた勉強会を開催するなどして、検討を重ねた。
・先進する欧米のものを見ると、ストーリー立てになっているものが多かった。そこで、「コミュニケーションブック」(ストーリー編)と、「S-BOOK」(パフォーマンス編=通常のCSRレポート)の二冊体制に変えた。これにウェブ版で基本情報を補完している。どのレポートも、ISO26000の七つの中核主題に基づいて体系的に整理している。
・「コミュニケーションブック」は社員、生産農家、顧客などステークホルダーとの対話ツールであり、ステークホルダー・エンゲージメントのツールと位置づけている。
・ストーリーは三部構成にした。 1)やっていることをアピールする(いいね!) 2)どうしてやっているのか、理由を述べる(なるほど!) 3)外部の評価も示す (またね!)――これで、読む人の頭に入りやすくなる。
・ストーリー展開を明解にするために、マテリアリティを絞り込み「茶畑から茶殻まで」(バリューチェーン)を消費者に示すことを主眼に据えた。
そして、大好きな映画を観ているように、幕開けのプロローグ、随所にフィルムを散りばめて社員や生産者の顔を写して展開し、エピローグでビロードの幕を閉じる、という工夫で一味加えた。
・営業マンに活用してもらえるように、どのストーリーからでも見せながら話ができるように心を配った。社長の誌面はトップである必要はなく、バランスを見て配置した。
・この「ストーリーブック」を効果的に使ってもらう策を講じた。まず、配布先は意志決定権がある幹部級にして、内容の説明をした。加えて、営業部隊への全国キャラバン「メイキング・オブ・ザ・CSR報告書」と題して、水平展開を図った。内容を理解した営業マンが説明すると大きな反響があり、営業ツールとして定番資料になった。 営業へのバックアップ体制も整備した。コミュニケーションブックの裏表紙に問い合わせ先電話番号を載せて、お客様からの問い合わせ対応をCSR推進部で行っている。
・一方、社内への浸透には、「コミュニケーションブック」の一つ一つのストーリーに必ず社員を登場させた。これにより関心が高まり、社員同士の見える化が進んだ。
・CSRレポートは、ステークホルダー・エンゲージメントの時代に入っている。統合報告の流れにあるように、財務情報だけ、またESGだけでは会社の顔は見えない。二つを合わせて、経営のストーリーを語ることを目指している。 ヨーロッパ主導のGRIの勉強を重ねて、経営の根幹を考えて行く作業を行い、ステークホルダーにわかり易く見せることが求められている。コミュニケーションを強化するには、社内外ともに対して、わかり易くなければならない。
そして陰徳ではなく、発信し続けること、さらに発信手法を磨いていくことが求められている。



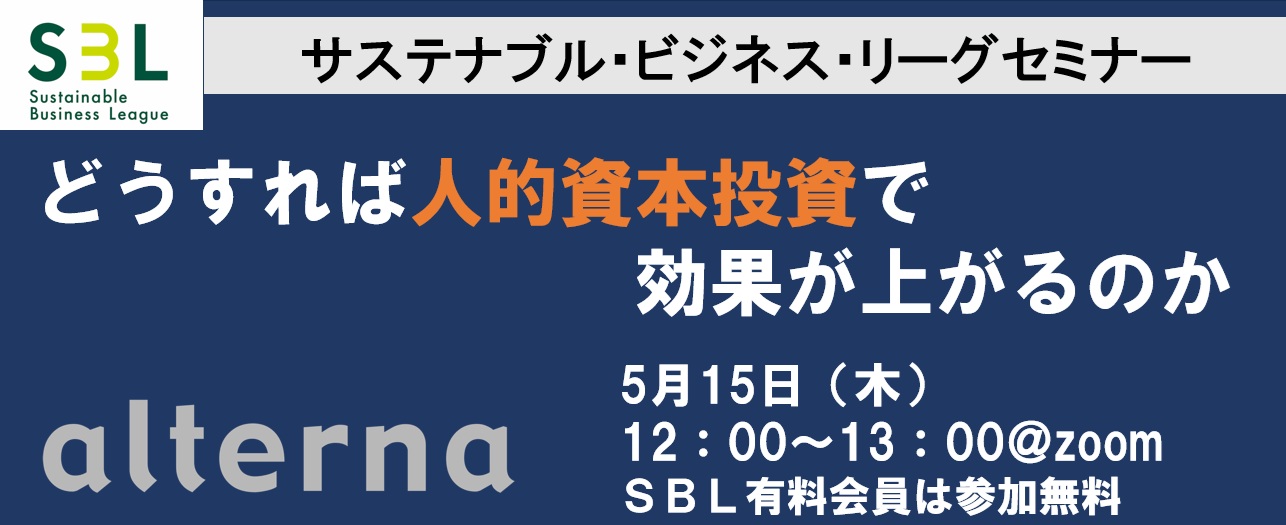


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























