米国では今、ダム建設一辺倒から、不要なダムの撤去へと方向転換している。その軌跡を豊かな自然の情景とともに描いたドキュメンタリー映画「ダムネーション」が22日から公開される。映画のプロデューサーで、来日中のマット・シュテッカー氏が21日、メディア取材に応じた。(オルタナ編集委員=斉藤円華)
■自然の美しさ描く

――本作品制作のきっかけは
「ダム建設の破壊性と、ダムの撤去後に自然が急速に回復するという、この事実を伝えたいと思った。パタゴニア(アウトドア衣料ブランド)創設者のイヴォン・シュイナード氏と意気投合して、映画制作を決めた。
米国では毎年、約50基のダムが撤去され、これまでに約1千カ所でかつての流れがよみがえっている。撤去作業でダム本体に穴をあけたところ、その3日後にサケが遡上した例もある。しかし米国でも20年前は、一度ダムを作ったら自然は元に戻らないと思われていた」
――取材したダムの数は
「50人以上にインタビューを行い、8基のダムに焦点を当てた。もう10基ほど取材したかったが、いろいろな制約があり断念した。ダム現地を訪れると、サケが遡上できないので生態系に悪影響が及んでいることが観察できた。また、ダムより上流の水質も悪化している。流域で暮らす先住民を巡っても、漁労で生計が立てられなくなる、世代間の継承が途絶えるなどの文化的な負の影響が生じている」
――ダムは文明社会に貢献してきた。有用なダムと無用なダムの線引きは
「かつてはダムに治水や発電等の効用があった。しかし、例えば治水では地下の帯水層を利用した貯水方法が既に確立されている。これならば大雨時にダムがあふれるなどの心配をしなくて済む。発電でも風力など、より環境負荷が低い自然エネルギーを利用できる。
そもそもダムは湖面からの蒸発量が多い。しかも堆砂によりやがて使えなくなる。ダムは水利用には適していない。
映画制作でとりわけ苦労したのは、ダム建設賛成派の政治家にインタビューを申し込んでも、ことごとく断られたことだ。しかしこれは、ダム推進派がダムを作る必要性を社会に対して説明できないことの証明ではないだろうか」



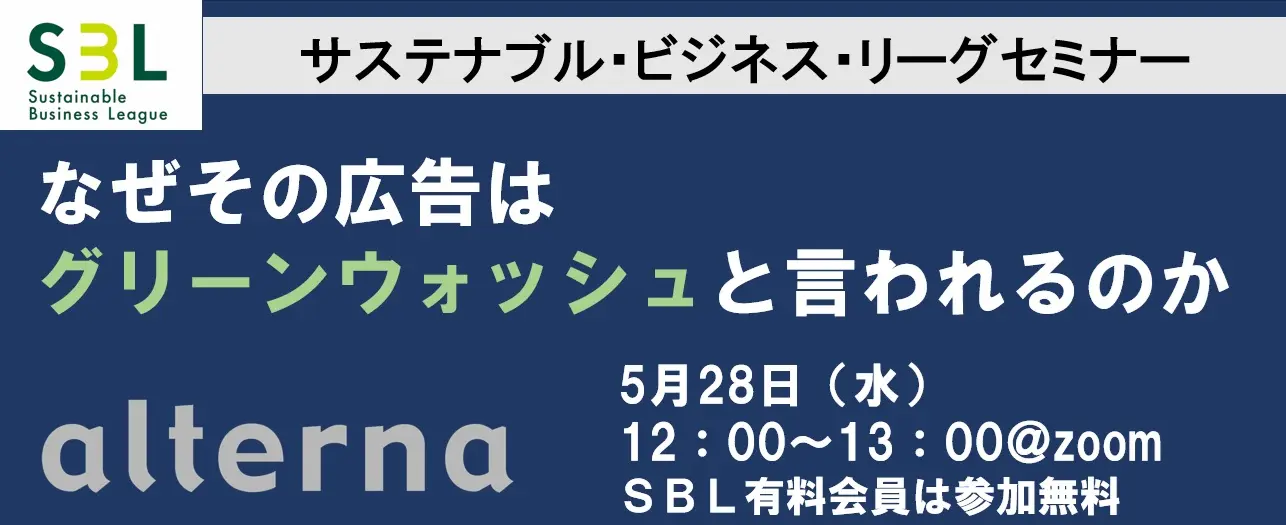


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























