東日本大震災から6年半が経過し、首都圏では震災や復興に関する情報やイベントに出合う機会は確実に少なくなっている。一方、豪雨被災など、これまで経験したことのないような災害が全国各地で起こり、もはや「被災地」というだけではどこの事かわからない。「風化」を止めることは、被災地のためだけではなく、自分自身の人生を守り、未来を切り拓くことにつながるということを、復興地での研修事例を通してあらためて考えさせられた。(一般社団法人RCF=荒井美穂子)
■労使一体で取り組む人材育成

5月下旬、サントリー食品インターナショナル労働組合のメンバー12人が研修で陸前高田市を訪れた。
震災直後は多くの企業が「ボランティア研修」として被災地を訪れたが、時が経ち現地ニーズも変化する中、活動に区切りをつける企業も多い。なぜ今なのか。企画に携わった川本氏は研修の狙いをこう語る。
「この研修で目指したのは気づく力・感じる力を高めることで、人間的な成長につなげること。『人間力』を高めることが仕事力の向上の元になる、という『五感塾』の内容を参考にしています」
五感塾とは、長年いすゞ自動車で企業人教育に携わってきた北村三郎氏が提唱している学習方法だ。地域の現場に身を置き、その地域に伝わる伝統文化やその地域のために働く志の高い人に触れ、体験を通じて学ぶことを奨めている。
一般的な企業研修では、仕事に直結する「スキルアップ」に重点が置かれがちだが、仕事の内容が複雑になるほど、課題解決の上で「人間力」が問われる場面も増えている。また、「個の成長」を通して「強い組織」を作るというのは、労使に関わらず共に目指す姿でもある。「数値化が難しい人間力の向上を労働組合の研修として実施することは、会社にとっても意義がある」(川本氏)。
参加者の自己負担もあることから、参加人数に不安もあったと言うが、募集開始5日で満員となり、参加できない社員からも、励ましのメールが届くなど社員からの反応も上々だった。
■被災地で聞く「決断」の重み
移動のバスの中では、参加者にあらためてこの研修で自分が何を目指すのかを考えさせた。「(被災地を)見て確認したい」という一歩引いた視点から、これから視察する内容を「自分事」としてとらえ、「当事者意識」で体感してもらうためのマインドセットの時間とすることで、移動時間の長さを逆手に取った形だ。
現地での受け入れは一般社団法人マルゴト陸前高田がおこなった。陸前高田で教育旅行や企業研修の受け入れやコーディネートをおこない、「学び」を核とする交流人口の拡大を目指している団体だ。
マルゴト陸前高田の伊藤雅人理事は「研修事業を通して自分たちが困難に立ち向かう中で得た『学び』や『生き抜く力』を多くの人たちに知ってもらい、陸前高田に継続して人が来る流れを作りたい」と語る。
研修では、戸羽陸前高田市長の講話の後、実際に津波で被災した現場に移動し、マルゴト陸前高田の伊藤理事や市内の事業者から当時の経験を聞く。一人一人がそれぞれの立場で「リーダー」として、経験したことのない非日常の中でひたすら「何ができるか」を考え、迷いの中で「決断」し「実行」した、そんな生の声を現場で聞くことで、その重みが更に心に響く。
ここでも移動時間や懇親会後の時間に意見交換をおこなった。想像以上の話を聞くことで、人によっては情報過多になり、整理がつかなくなる場合もある。その場で感じたことを「言語化」することで、体験を消化し、その内容を可視化しておくことで、研修としてしっかりと記憶や心に「残す」ことを目指した。
■自分事への転換が「行動」を促す

研修を振り返って川本氏は「研修を体験し、現地の方々の生の声に触れることで、決断する大切さ、重みを学んだ。加えて、それまで他人事だった事が自分事となることで、人を認め合う気持ちや発想力が広がり、その場で宣言したことを行動に移す実行力が現れるなど、事務局が想定していた以上に参加者の変化が見られた」と語った。
災害への備えとして、常日頃から想像力を働かせ、自分の環境に置き換えて対策や行動をイメージしておくことが重要と言われる。今回の研修で参加者が得た体験は、災害を「自分事」として備え、万が一の時に困難を乗り越える力として役立つに違いない。また、その力は、変化が加速する現代において、今後参加者たちが仕事や地域で出合うさまざまな課題を解決する上でも大きな力となるだろう。



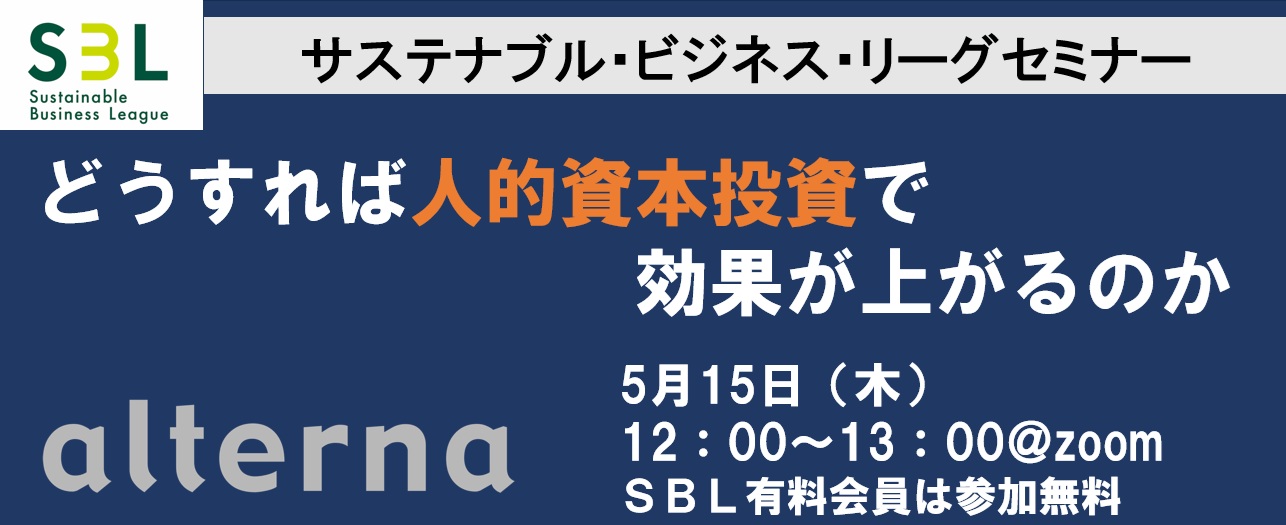


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























