林業は危険な仕事、と言われてもあまりピンとこない人が多いかもしれない。一般の人にはなじみのない数字だが、労働災害の発生状況を評価する指針の一つに「年千人率」がある。これは、1年間の労働者1000人当たりに発生した死傷者数の割合を示すもの。ちなみに2017年の数字を紹介すると全産業で2.2人のところ、林業はなんと32.9人ともっとも悪い数字を記録している。次に悪い数字の製造業の木材・木製品が9.9人だから、その異常さが分かる(厚生労働省「職場のあんぜんサイト」平成29年労働災害統計)。

■もっとも危険な仕事、それは林業?
何故、こんなに重大災害が起きているのだろうか。ほとんどの伐倒作業は、傾斜の急な足場の悪い林内で、チェーンソーを使って行う。この作業が危険を伴うことは、素人でも容易に想像できる。さらに、林業従事者の高齢化や新規参入者への十分な教育という課題がある。
■伐倒時の事故をなくすための動き
厚生労働省でもこの問題を深刻に捉え2017年11月から有識者を集め「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会」を開き、2018年3月に「伐木等作業における安全対策のあり方に関する検討会報告書」を公開した。報告書のポイントは下記の通り。
1 チェーンソーによる伐倒時に受け口を作るべき立木を、胸高直径40cm以上から20cm以上とすること
2 チェーンソーによる伐倒時に、伐倒木の高さの2倍の範囲を立入禁止にすること
3 かかり木処理の方法として、かかられている木の伐倒、浴びせ倒しを禁止すること
4 チェーンソーによる伐木等作業時に、下肢を防護する防護衣の着用を義務付けるべきこと
5 チェーンソーによる伐木等作業に係る教育の充実を図ること
(厚生労働省 報道発表資料より)
また、厚生労働省は2012年度以降、林業の安全対策に関する技術的検討を進めていて、2015年に「チェーンソーによる伐木等作業に関するガイドライン」を取りまとめた。
この報告書やガイドラインについては業界で様々な意見が出されているが、ここではそれには触れない。ただ、上記の報告書のポイントを見てもわかる通り「~とすること」「~禁止すること」「義務付けること」などいかにも「お上」からのお達し然としている。もちろん間違ってはいないと思うが、これだけで本当に林業の労働災害を減少することができる
だろうか。

■安全を根本的に見直す
2016年の12月、岩手県九戸郡洋野町にある筑波重工で、一つのプロジェクトが生まれた。岐阜県郡上市の林業家で現在は日本各地で指導者や初心者向け研修の講師を務めている、Woodsman Workshopの水野雅夫氏が考案し、筑波重工社長の小田直樹氏が製作し、丸大県北農林の大粒来宏美氏の協力のもとに生まれた伐倒練習機開発プロジェクトだ。
水野氏は、伐倒作業時の事故の原因に「伐倒作業に対する認識の甘さ」と「伐倒技術の未熟さ」を挙げている。そして、初心者に対する技術教育や基礎訓練が不十分であることを指摘している。
スポーツを例にとれば、野球でもゴルフでも、試合に出場する前にバットやクラブの持ち方、姿勢を教え込まれ、素振りを繰り返し、フォームを身体で覚えてどんなときでも体がブレないようにするのが基本だろう。
ところが林業の現場ではどうかというと、林内で練習に適した立木で探して伐倒の練習をするが、初心者の練習に適した立木は決して多くはない。本来なら、基礎技術をしっかり身に付けてから現場作業を行うべきだが、実情は十分とは言えない習熟度のまま現場での伐倒をさせられるケースが多い。OJTといえば聞こえがいいが、危険が大きい。
また、指導者の未熟な指導方法も問題だ。16年前に「緑の雇用」事業が始まって、外部から若者が林業に就業するようになったが、それまでは父や祖父を見て作業を覚えてきたという人が多かった。体系だった指導方法などは確立していなかったといっていい。現在では、かなり指導方法も拡充してきているが、練習するための立木が少なく、またあったとしてもそこに移動するのに時間がかかってしまい、十分に練習させられないという状況に変わりはない。
■斜面における「水平感覚」と「作業の再現性」



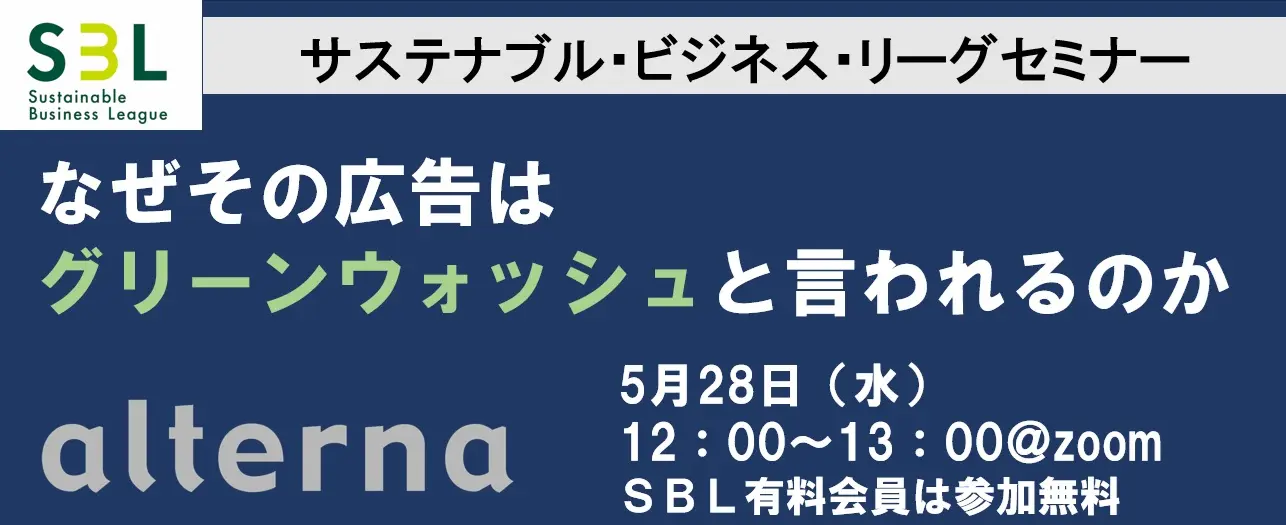


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























