森づくりには、とてつもない時間がかかる。苗を植えただけでは森にならない。植えた苗が育ち、森となるまでは数十年から百年はかかる。それだけに森づくり活動というのは、成果を見ることが難しい活動だ。何千本、何万本、苗を植えてもそれが森と呼べるまで育つかどうかは、わからない。数年前に植林したフィールドを2018年の暮れに視察した。

過去を振り返るセンチメンタル・ジャーニー
2018年の年の暮れに、過去の植林フィールドを見て回る日帰りツアーに参加した。NPO法人 森のライフスタイル研究所では、2010年から2015年にかけて長野県各地で森づくり活動を行った。廃業したスキー場のゲレンデに木を植えて森に還す活動を行った長和町和田峠スキー場跡地、山火事に遭った森を子どもたちの遊び場になるようにドングリのなる木を中心に植えた東御市北御牧地区・田之尻の活動、人の手が入らず荒廃した人工林の再造林を実施した佐久市大沢財産区での活動などで、一般市民や企業からのボランティアの手で木を植えてきた。
植樹後も、数年間は夏に下草刈りを行ったが、現在は活動を終了している。これらの場所が「今、どんな状態になっているか。ちゃんと森になっているのかを見てみよう」と長野県林業総合センターの小山泰弘農学博士の提案により視察ツアーを企画した。参加したのはNPOから2人、一般参加で私を入れて4人、小山先生の合計7人。新幹線佐久平駅に現地集合しNPOの車に同乗して和田峠、田之尻、大沢の順番で視察した。

初期保育の次を考える
森づくりというと普通の人は木を植えることのみを連想し、それを期待する。したがって植樹活動に参加したいという方は多いが、木を植えるとたいてい満足してしまう。
ところが、森づくりは植えてからが本番で、一般的に30年ぐらいは人が手をかけてやる必要がある。とくに植えてからの5〜7年間は、暑い夏の盛りに下草刈りを行い、雑草や灌木に覆われた苗に日光が当たるように世話をする必要がある。これを怠ると雑草の海にのみこまれて苗に日光が当たらず(光合成ができず)生育が悪くなり、最悪枯れてしまう。こうなってしまってはせっかく費用と人力をかけて植樹をしても元の木阿弥になる。
とはいえ、夏に雨が多く比較的温暖な日本では、何も植えなくても木は生えてくる、と思う。ケースバイケースだが、より自然に近い森をつくるならいっそ植えずに自然に任せた方がいいのかもしれない、と個人的には思ったりもする。しかし、それでは思い通りの森にはならない。したがって「将来、木材を生産したい」だとか、「薪や炭を産出したい」という森をつくるには、木を植えてからもずっと世話(保育作業)をしていく必要がある。今回、見て回った森は、初期の保育期間(下草刈り)を終え、次の段階に入った森と言える。森の現状を確認すると同時に、健全な森に育てるためのこれからの施策を考えてみたいと思った。


その1 和田峠スキー場跡地を森に還す活動



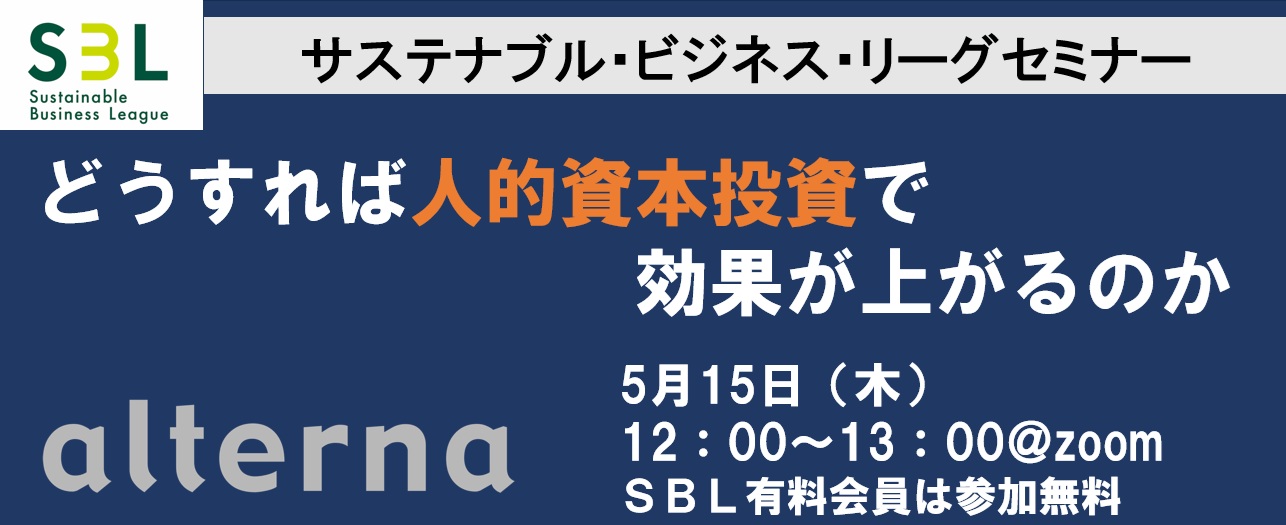


-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























