■編集長コラム
斎藤幸平・大阪市立大学大学院経済学研究科准教授の『人新世の「資本論」』が20万部以上売れ、話題を集めています。この著書を知ったのは「SDGsは大衆のアヘンである」という記述があると聞いたからです。この連休に同書を読み、感想をまとめてみました。(オルタナ編集長・森 摂)
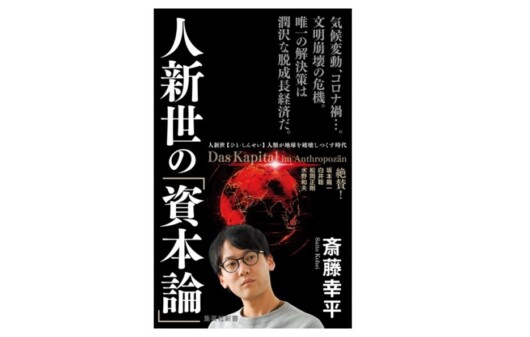
この本を私なりにまとめると、
1)いま各国政府や企業が取り組んでいる気候変動対策では地球温暖化を止めることはできない
2)温暖化を止めるためには、資本主義そのものを見直す必要がある
3)カール・マルクスの「資本論」の再解釈を通じて、「脱成長のコミュニズムを目指すべき」――という流れです。
前半はさまざまなファクトを多く引用し、気候変動がもたらす「不都合な真実」が並べられています。デビッド・ウォレス・ウェルズの『地球に住めなくなる日』を思い起こしました。
『人新世の「資本論」』の冒頭には、「かつてカール・マルクスが、資本主義の辛い現実が引き起こす苦悩を和らげる「宗教」を『大衆のアヘン』だと批判したことになぞらえて、「SDGsはまさに現代版『大衆のアヘン』である」ーーとの記述があります。
この表現を見た時に、最初は違和感を持ちました。真面目にSDGsに取り組んでいる自治体や企業もある中で、それらの努力を全否定しかねない表現だったからです。
SDGsは決して苦痛を和らげてはくれないし、かつて英国が「清」を蝕んだような、西欧列強による途上国侵略の手段でもありません。SDGsは2015年当時の国連全加盟国193カ国が全会一致で採択した世界共通のゴールです。
ただ、やはり「SDGsに取り組んでいます」というアピールだけして、行政やビジネスの手法を根本からサステナブルにすることがない実例を見るにつけ、それは「グリーンウォッシュ」であり、「SDGsウォッシュ」であるという気持ちにはなります。
■「デカップリング」の答えは出ていない
むしろ納得できなかったのは、同書では、経済成長を達成しながら温室効果ガスの排出量を減らすという「デカップリング」を否定していることです。
英国など欧州のデカップリングは認めているものの、「世界規模で見れば新興国における著しい経済成長のために、二酸化炭素の排出量は増え続けている」と主張します。
これについて、私の持論は「まだ答えは出ていない」ことです。米国では温室効果ガスの排出が2007年以来、日本でも2013年以来、減り続けています。
日米欧のノウハウを途上国に供与して、経済成長と温室効果ガスの削減を両立させることは可能だと考えます。もちろん、その道は険しいですが、不可能ではないと思います。
※日米欧の温室効果ガス排出量推移
日本: https://www.jccca.org/download/13334
米国: https://www.c2es.org/content/u-s-emissions/
EU: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-4a.html





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























