児童養護施設出身のモデル田中麗華さんが12月6日、自身の生い立ちをまとめた著書『児童養護施設という私のおうち』(旬報社)を発売しました。田中さんは7歳から18歳まで都内の児童養護施設で育ちました。現在は、モデル活動に加えて、ユーチューバーとして、親元を離れて暮らす子どもたちへの理解の輪を広げる活動を行っています。(オルタナS編集長=池田 真隆)

著書では、施設で暮らすことになった経緯から施設内での日常、卒園後の苦悩などを赤裸々に明かしています。児童養護施設の存在は多くの人が認知していますが、実際に園内で子どもたちがどのように暮らしているのか理解している人は少ないでしょう。著書は、児童養護施設とそこで育つ子どもの全体像を知るための「入門書」です。
2018年に田中さんを取材したのですが、施設で暮らす子どもたちのことを「社会的弱者」と言う世の中に違和感があると強調していました。
「私たちのことを知らないから、施設出身者を一様に社会的弱者とまとめているのではないか。施設出身者だから、苦労したと決めつけてはいないか。それぞれ異なる境遇を育ってきたので、一人ひとりとしっかりと向き合い、話を聞いてほしい」と語っていたことが印象に残っています。
そんな、田中さんの著書の一部を先行公開します。
最終回となる第4回は、「帰りたいけど、帰れない」です。
*第3回「高校生になって感じた職員との距離感」からの続きです。

■帰りたいけど、帰れない
短大時代は、施設には全然帰っていませんでした。職員のシフトを考えると、会いたいと思っている先生がその日にいるとは限らないことがハードルとなって、施設から自分を遠ざけていったような気がします。育ったところなのに、気軽に行けない気がしていました。
その一方で、施設の先生からは18歳、19歳、20歳までの3年間、誕生日の日にバースデーカードが届いていました。施設を出てからは一人で誕生日を過ごすことが増えたので、それがとってもうれしく、それを読んでは、部屋の中で泣いていました。「一人だけど一人じゃない。でも一人だ……」って。
一度だけ先生が家に来てくれたこともありました。その先生とは施設を出た後、手紙のやりとりをしていたので、忙しい中来てくれたことがうれしかったのを覚えています。そのとき、先生が私の家でご飯を作ってくれたのですが、久しぶりに食べる「誰かの手作りご飯」は言葉にできないくらい美味しくて、温もりを感じました。そして、それまで気負っていた「大人でいなきゃいけない」気持ちがそのときだけはスーッとなくなって、久しぶりに自然体でいられました。
また、短大の留年が決まった頃、そのことをたまたま私の大学の職員から聞いた中野先生が「こういう支援があるから受けてみない?」と連絡をくれて教えてくれたのが「せたがや若者フェアスタート事業」という取り組みでした。
「せたがや若者フェアスタート事業」は、施設出身の子どもたちへ一人暮らしの家賃補助や給付型奨学金、居場所づくりなどを複合的に行うという内容の支援です。奨学金は学生向けで、家賃補助は働いている人も対象です。居場所づくりというのは、「若者版子ども食堂」みたいなものでしょうか。
私の生活条件だと家賃補助の支援対象だったので、毎月1万円で家を借りられるという支援を受けることにしました。それをきっかけに施設と連絡を取ることも増えてきて、再び「おうち」とつながるようになりました。
★★★
田中さんは現在、クラウドファンディングに挑戦中です。集めた資金で、この本を子ども支援団体や小中学校に寄贈します。詳しくはこちら





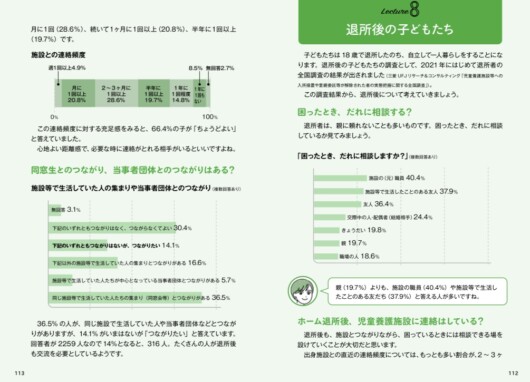

-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























