オルタナは月1回、サステナビリティのホットトピックをゲストと話し合うSBL(サステナブル・ビジネス・リーグ)セミナーを開いている。20回目となる4月26日は、ドイツ在住の環境ジャーナリスト・松田雅央(まさひろ)さんを招き、ウクライナ戦争がドイツのエネルギー政策に与える影響や、再エネシフトの最前線について伺った。(オルタナ副編集長・長濱慎)
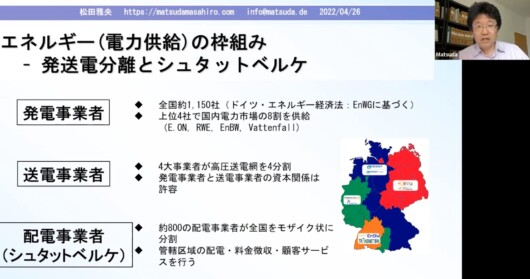
松田さんは1995年にドイツに渡り、南西部の都市カールスルーエを拠点にヨーロッパのエネルギー環境政策や都市計画について情報を発信。時差が約7時間の現地からオンラインで、1)ウクライナ戦争がドイツに与えた影響、2)脱原発、3)再エネシフト、4)エネルギー政策の背景について解説した。
1)ウクライナ戦争でも脱石炭・脱原発は変わらず
ドイツは天然ガスの55%をロシアに依存(2020年)しており、戦争によって供給が絶たれたことで石炭火力の発電量が増加。22年末に全基停止予定の原子力発電の運転を1〜2年延長する可能性も出てきた。
しかし、これはあくまでも一時的なもので、脱石炭(2038年まで)と脱原発という基本方針は変わらない。とくに連立与党の「緑の党」は、原発の運転期間延長に否定的である。
2)脱原発・メルケル前首相は「原発推進派」だった
日本ではメルケル前首相が脱原発のリーダーのように語られ「2011年の東日本大震災・東京電力福島第一発電事故をきっかけに全廃に踏み切った」というのが定説になっているが、事実は少し異なる。
ドイツでは1970年代から脱原発運動が始まり、その機運は86年のチェルノブイリ事故でさらに高まっていた。最初に原発の全廃を決めたのはシュレーダー政権(2002年)で、メルケルは推進派だった。
メルケルは2010年、国民の反対を押し切って平均12年の原発の運転延長を決めた。しかし翌年に起きた福島第一原発事故を受け、急きょ原発廃止に方針を転換した。「この決断力の速さとリーダーシップは見習うべき」と、松田さんは語る。
3)再エネは「脱原発、省エネ」とセットの政策
ドイツは再エネシフトを脱原発とセットで進めている。2020年の再エネ発電比率は約45%で、30年には65%を目指す。これにエネルギー効率化(省エネ)を組み合わせた、総合的なエネルギー政策がドイツの特徴である。
再エネの電力で水素を作り、それを原料にメタノールなどの燃料を合成する「Power-to-X」と呼ばれる取り組みも始まっている。日本では「再エネ=電気」というイメージが一般的だが、ドイツでは熱分野でも再エネの活用を進めようとしている。
4)環境大国・ドイツの根底にある市民の「環境意識」





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























