記事のポイント
- 非営利組織が日本のファッション業界の課題をレポートでまとめた
- レポートでは「完璧主義」がもたらす日本の遅れを指摘した
- 企業に求められているのは「完全性ではなく透明性」と強調
英国の非営利団体ファッションレボリューションの日本支部はラナ・プラザ崩落事故から10年を迎える節目に、日本のファッション産業が抱える課題と改善策をまとめたレポートを発行した。2013年4月に起きたラナ・プラザ崩落事故では1132人が命を落とした。レポートでは、「完璧主義」がもたらす日本のファッション産業の遅れを指摘した。重要なことは「完全性よりも透明性」とし、そのためには成果を自慢するよりも、欠点を認めることが社会から信頼を得るカギだと提案する。(オルタナ編集部=池田 真隆、下村 つぐみ)
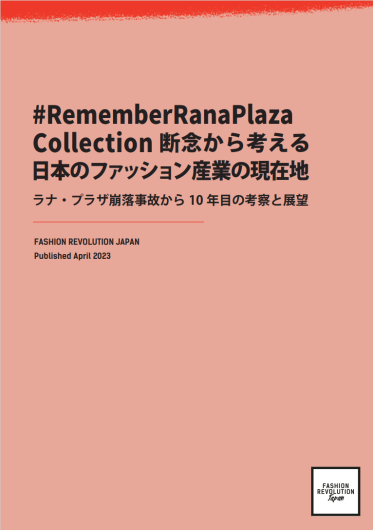
2013年4月24日にバングラデシュ・ダッカで発生したラナ・プラザ崩壊事故は、歴史上最大の産業災害の一つだ。ラナ・プラザは銀行やアパート、縫製工場などが入った8階建ての建物だ。
崩落によって、縫製工場で働く約5000人の労働者のうち、1132人が死亡し、約2500人が負傷、100人の行方不明者をだした。
崩落する前日、建物内に大きな亀裂が見つかった。もともとこの建物は4階建てで、4階分は違法に増築していた。崩落の危険性から、銀行や店舗はすぐに営業を停止した。
しかし、縫製工場の経営陣は危険性を認識していながらも、労働者に働くことを求めた。海外バイヤーからの「納期に間に合わせろ」というプレッシャーからそう決断したとされている。
労働者たちは、働きに行かなかったら賃金が支払われないかもしれないと感じ、危険性を感じながらも働いた。
崩落事故後、ガレキの中から見つかったのは、世界的に有名なファストファッションブランドのタグだった。その中には、国内ブランドもあった。
事故を検証していく過程で明らかになったのは、これらのブランド自身がこのタグを見て、初めてラナ・プラザの工場で自社の製品が作られていたと知ったことだ。つまり、ブランド自身がサプライチェーンを把握せずに、製品を販売していたのだ。
■ラナ・プラザをきっかけに社会運動が100カ国に広がる
この事故をきっかけに2014年に英国で生まれた社会運動が「ファッションレボリューション」だ。ファッション産業にサプライチェーンの透明性を求めるキャンペーンを展開する。現在は日本を含む100カ国に広がる。
日本支部はラナ・プラザ崩落事故から10年を迎える節目に合わせて、業界横断型のキャンペーンを考えていた。1着の服の生産背景を長いタグで可視化するものだ。事故から10年が経ち、サプライチェーンの透明化がどれだけ進んだのかを社会に示すことが目的だった。
当初は多くの企業から賛同を得た。だが、実現には至らなかった。企業アンケートでは、「サプライチェーンを把握していないから」「グリーンウォッシュになるリスクがあるから」「情報開示を必要だと考えていないから」——という3つの理由が分かった。
企画倒れにはなったが、日本支部はこのアンケート結果をもとにレポートをつくることを決めた。日本のファッション産業が抱える課題をまとめ、改善策を提案した。
■透明性への「3つの指針」





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























