記事のポイント
- LGBTQ当事者やアライを支援する動きは、教育機関にも広がっている
- 中央大学は、一橋大学アウティング事件をきっかけに対応を本格化させた
- 困りごとに対応するために、本人の同意を得たうえで、大学内で連携している
LGBTQ当事者を支援し、受け入れ体制を整える動きは、教育機関にも広がっている。中央大学や早稲田大学などは専門のセンターを開設したほか、大学関係者による「大学ダイバーシティ・アライアンス」(UDA)も生まれた。(オルタナ副編集長・吉田広子)
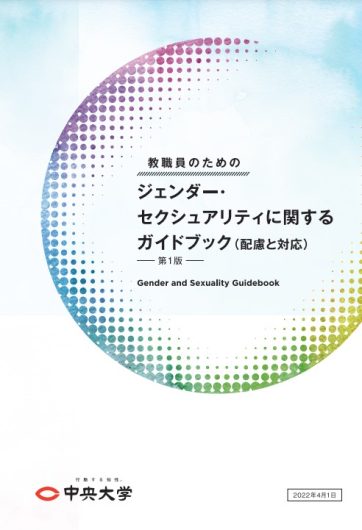
2015年8月、一橋大学法科大学院に在籍していた男子学生Aさんが校舎から転落し、亡くなった。同級生の男子学生Bさんに告白をともなうカミングアウトをしたところ、LINEの「グループ」で暴露され、心身の不調に陥った。
Aさんは大学のハラスメント相談室に相談していたことから、遺族は大学の法的責任を追及する民事訴訟を起こした。裁判所は、一橋大学の法的責任を認めなかったものの、「許されない行為であることは明らか」と違法性に言及した。
この事件が広く報道されたことで「アウティング」(本人の同意を得ない暴露行為)は「命にかかわる重要な問題」だと認識されるようになった。
Aさんの出身校である中央大学は、この事実を重く受け止め、本格的に環境整備を進めた。17年10月に公表していた「ダイバーシティ宣言」を受けて、20年4月にはダイバーシティセンターを開設した。
22年4月には、ジェンダー、セクシュアリティについて分かりやすく解説したハンドブックを学生、教職員向けにそれぞれ作成した。基礎知識や学生生活に関わる情報、相談窓口などについて掲載している。
■本人の同意を得た上で専門チームが連携

中央大学ダイバーシティセンターには、年間70件ほどの相談が寄せられる。





-1-scaled.jpg)

-scaled.jpg)


























